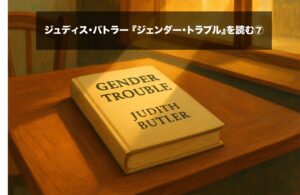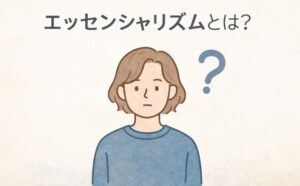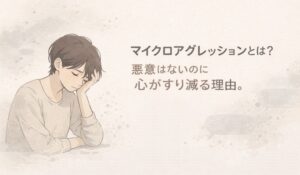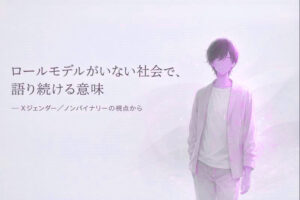ノンバイナリーとは、性自認が「男性」「女性」のどちらにも完全には当てはまらない人を指す言葉です。
男女の二択に収まらない性のあり方を含む概念で、「中性」「無性」「流動的」など多様な感覚が含まれます。
日本では「Xジェンダー」と近い意味で使われることもありますが、
ノンバイナリーはより広く、世界的に使われている言葉です。
私自身、30歳を過ぎてから「本当に自分らしい生き方って何だろう?」と考え直すなかで、この言葉に出会いました。
ノンバイナリーを知ることは、自分の違和感に名前を与え、少しずつ心が軽くなるきっかけにもなりました。
この記事では、
- 自分の性別にしっくりこない
- 「男」「女」どちらにも違和感がある
- ノンバイナリーという言葉を見かけて気になっている
そんな思いを抱えている人に向けて、できるだけわかりやすく、そして私自身の体験も交えながら丁寧に解説していきます。
ノンバイナリーとは?
ノンバイナリー(non-binary)とは、
性自認が「男性」「女性」という枠にあてはまらない人を指す言葉です。
性別を「男か女か」の二択で考える価値観を「ジェンダーバイナリー(二元論)」と言いますが、
ノンバイナリーはその枠の外にある多様なあり方を尊重する概念です。
たとえば、
「自分は男性でも女性でもない」
「そもそも性別というものを意識していない」
「一つの性別でくくられることに違和感がある」
など、その感覚は人によってさまざまです。
ノンバイナリーはまだその存在の認知度が低いことから、「いないもの」のように扱われてしまうという社会的な問題があります。
例えば、ノンバイナリーの人の中には性別欄に「男・女」しかないことに困ったり、トイレや更衣室が男女のみに分かれていて使いにくいなどの不便さを抱えている人もいます。
これをノンバイナリー・インビジビリティといいます。
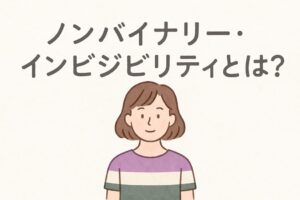
また、見た目にはノンバイナリーであることがわかりにくいことに悩みを抱える人もいます。
私自身も「ノンバイナリーらしさ」を探求している最中です。
「ノンバイナリーらしさ」って何だろう?というテーマについてはこちらでまとめています。

どんな人がノンバイナリーに当てはまるのか
ノンバイナリーという言葉を知ったとき、
あなたはどんな気持ちになったでしょうか。
「やっと見つけた気がした」
「でも、自分が当てはまるのかはよくわからない」
「しっくりくるような、こないような……」
そんなふうに、少し安心しつつも戸惑いを感じた人も多いかもしれません。
ノンバイナリーには、
「こう感じていれば必ず当てはまる」という明確なチェックリストはありません。
ただし、当事者の声を見ていくと、共通しやすい感覚や悩みの傾向はいくつかあります。
ここでは、「診断」ではなく、
自分の感覚を確かめるためのヒントとして紹介します。
「男」「女」のどちらにも、しっくりこない感覚がある
- 自分を「女性」「男性」と呼ばれると違和感がある
- どちらかに分類されること自体が落ち着かない
- 選択肢が二択しかない場面で、いつも迷ってしまう
- 一つしか選べないことに困ってしまう
この違和感は強烈なこともあれば、
「なんとなくモヤっとする」「言葉にできない違和感」として現れることもあります。
はっきりした拒否感がなくても、
「どちらも違う気がする」あるいは、「どちらも当てはまる気がする」という感覚は、ノンバイナリー当事者に見られる特徴の一つです。
性別で期待される役割や振る舞いが、重く感じる
- 「女の人なんだから」「男ならこうするもの」という言葉に息苦しさを感じる
- 性別を理由に役割や性格を決めつけられるのがつらい
- 無意識のうちに「その枠に合わせよう」として疲れてしまう
これは単なる「ジェンダー規範が苦手」という話にとどまらず、
自分の存在そのものが、型に押し込められている感覚につながることがあります。
性別を意識しないでいられる瞬間に、ほっとする
- 性別を聞かれない場では気持ちが楽
- オンラインや匿名の空間の方が自然体でいられる
- 性別を前提にしない関係性に安心感を覚える
「性別を表明しなくていい」
「どちらとして振る舞わなくていい」
そんな状態のときに心が軽くなるなら、
性別という枠そのものに違和感を抱いている可能性があります。
日や場面によって、性別の感じ方が変わることがある
- ある日は女性寄り、ある日は男性寄りに感じる
- 時期や環境によって、性別への意識が揺らぐ
- 「今日はどっち?」と自分に問いかける感覚がある
こうした揺らぎは、
ジェンダーフルイドやバイジェンダーなど、
ノンバイナリーの中の多様な在り方とも重なります。
常に同じ感覚でいなければならない、ということはありません。
「当てはまらない部分」があっても、間違いではない
ここまで読んで、
- いくつか当てはまる
- ひとつも当てはまらない気がする
- よくわからない
どれであっても、問題ありません。
ノンバイナリーは、
誰かに当てはめられるラベルではなく、
自分の感覚を言葉にするための選択肢のひとつです。
今はまだピンとこなくても、
後から「そういうことだったのか」と腑に落ちることもあります。
「まだわからない」状態も、立派な現在地
性別について考えることは、
すぐに答えが出るものではありません。
- わからない
- 決めたくない
- 今は保留にしたい
そんな気持ちも含めて、あなたの感覚です。
ノンバイナリーという言葉は、
答えを急がなくていい場所をつくるための言葉でもあります。
モヤモヤしたままでも大丈夫。
その揺らぎごと、大切にしていいのです。
ノンバイナリーに関するよくある誤解
ノンバイナリーという言葉が少しずつ知られるようになる一方で、
実際の当事者の感覚とはズレたイメージが広まっているのも事実です。
ここでは、特によく聞かれる3つの誤解について、ひとつずつ丁寧に整理します。
ノンバイナリー=見た目が中性的、ではない
「ノンバイナリー」と聞くと、
中性的な服装や髪型を思い浮かべる人も多いかもしれません。
しかし、ノンバイナリーは“見た目”ではなく“内側の感覚(性自認)”を指す言葉です。
ノンバイナリーの人の外見は本当にさまざまで、
- 一般的に「女性的」とされる服装をしている人
- 「男性的」と見られやすい格好をしている人
- 日によって服装のテイストが変わる人
- あえて性別を意識させない服を選ぶ人
など、決まった型はありません。
周囲からは「一見わかりにくい」ことも多く、
そのこと自体が悩みや生きづらさにつながる場合もあります。
「見た目で判断できない」というのは、ノンバイナリーの大きな特徴のひとつです。
ノンバイナリー=トランスジェンダー、ではない
ノンバイナリーは、広い意味ではトランスジェンダーの枠組みに含まれることがあります。
ただし、すべてのノンバイナリー当事者が自分をトランスジェンダーだと捉えているわけではありません。
トランスジェンダーは一般に、
- 出生時に割り当てられた性別と
- 自分の性自認が一致しない
という状態を指します。
一方でノンバイナリーの中には、
- 男性・女性のどちらにも当てはまらないと感じている人
- そもそも「性別」という枠組み自体にしっくりきていない人
- トランジション(医療的・社会的移行)を望まない人
も多くいます。
そのため、
ノンバイナリー=必ずトランスジェンダー
ノンバイナリー=性別移行をする人
という理解は正確ではありません。
どの言葉で自分を表すかは、本人が選ぶものであり、
外から決めつけられるものではないのです。
ノンバイナリー=恋愛しない、ではない
「ノンバイナリーの人って、恋愛しないの?」
という質問も、よく聞かれる誤解のひとつです。
結論から言うと、ノンバイナリーと恋愛の有無は直接関係ありません。
ノンバイナリーの人の中には、
- 恋愛感情を持つ人
- 恋愛はするが性別は関係ない人
- 恋愛感情がわかりにくい人
- 恋愛よりも友情やパートナーシップを重視する人
など、さまざまな在り方があります。
恋愛しない、あるいは恋愛感情を感じにくい場合は、
アロマンティックやアセクシャルといった**「性的指向・恋愛指向」の話**になります。
つまり、
- ノンバイナリー → 性自認の話
- 恋愛する・しない → 恋愛指向の話
であり、これは別の軸の話なんですよね。
誤解をほどくことは、「安心して名乗れる社会」につながる
これらの誤解は、悪意から生まれているとは限りません。
多くの場合、「知らないこと」から来ています。
だからこそ、
正確な情報が共有されること、
一人ひとりの感じ方が尊重されることが大切です。
ノンバイナリーは、
特別な見た目や生き方をする人のことではありません。
ただ、自分の性別の感じ方が「男/女」という枠に収まらない人たちのこと。
そのシンプルな理解が広がることが、
誰にとっても息のしやすい社会につながっていくのだと思います。
ノンバイナリーとXジェンダージェンダーとの違いとは?
日本では「ノンバイナリー」に似た概念として「Xジェンダー」という言葉もあります。
| 観点 | ノンバイナリー | Xジェンダー |
|---|---|---|
| 起源 | 英語圏(グローバル) | 日本発祥 |
| 分類 | 分類しない自由を重視 | さらに中性・両性・無性・不定性などに分かれる |
| 対象 | 性自認と性表現を含む | 性自認中心 |
ノンバイナリーはどう振る舞うか(性表現)を含むのに対して、Xジェンダーは「自分の性別の感覚」に注目している、という違いがあります。
Google検索の検索されている件数を「ノンバイナリー」と「Xジェンダー」比べてみると、日本では「Xジェンダー」の方が検索数が多いです。とはいえ、どちらの言葉も、日本での認知度は低く、存在を知らない人の方が多いのが現状です。
Xジェンダーについては、こちらでも詳細を書いています↓
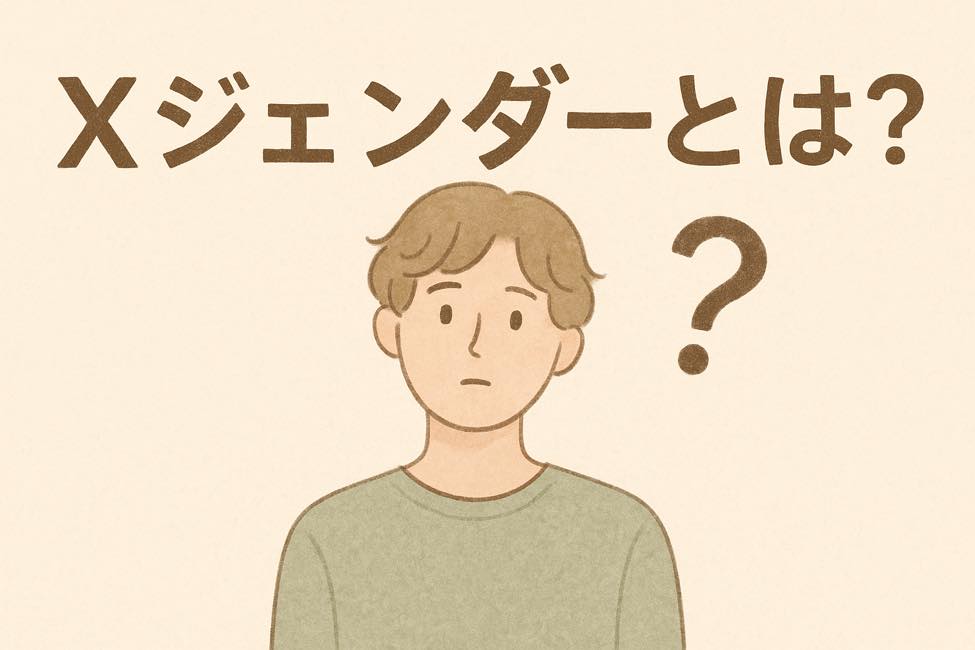
ノンバイナリーの種類と広がり
ノンバイナリーは単一の性自認ではなく、
幅広いアイデンティティを含む総称です。
そのため「ノンバイナリー」と一括りにしても、
その中にはさまざまな感じ方・あり方が存在します。
ノンバイナリーの中にある感じ方:
- エイ(ア)ジェンダー(Agender):性別という概念自体を感じない
- バイジェンダー(Bigender):2つの性を同時に、あるいは交互に感じる
- ジェンダーフルイド(Genderfluid):時間や状況で性自認が変わる
- デミジェンダー(Demigender):「なんとなく近い」性を感じるが断定しない
これらの感覚は外見では判断できず、本人の内面に根ざしています。
誰かがどんな見た目をしていても、「その人が自分をどう感じているか」が一番大切なのです。
エイ(ア)ジェンダーについては、こちらの記事でまとめています。

ノンバイナリーの代名詞と国ごとの言葉の違い
ノンバイナリーの人は、英語では「they/them」を使うことが多く、これは2019年にMerriam-Webster辞書にも正式に登録されました。
代名詞は、その人の尊厳に関わる大切な要素です。以下のような中性代名詞が使われることもあります:
- xe/xem/xyr
- ze/hir/hirs
また、国によって独自の代名詞も発展しています。
- スウェーデン:「hen」
- フィンランド:「hän」
- フランス:「iel」(若年層を中心に広がり中)
日本語では中性の代名詞が確立されておらず、「わたし」「ボク」「オレ」なども性別を連想させやすいため、ノンバイナリー当事者が悩みを感じやすいポイントになっています。
しかし最近では、日本でも彼、彼女の代わりに「彼人(かのと、かのひと)」や
おねえさん、お兄さんの間の「おぬうさん」など、
新たな言葉も生まれているようです。
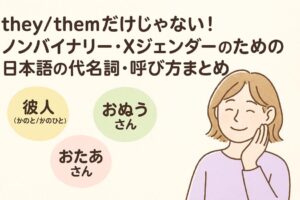
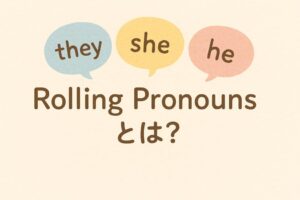
世界と日本で進む認知と制度の変化
アメリカ、カナダ、ドイツ、ニュージーランドなどでは、
パスポートに「X」性を記載できる制度が始まっています。
これは国レベルで「男/女以外の性」を認める動きと言えます。
また、大手の辞書や政府機関、メディアでも中性代名詞の使用が拡がり、「性別=2択ではない」という考え方が主流になりつつあります。
一方で日本では、法的な性別欄に第三の選択肢はまだなく、公的書類や制度面では課題が残っています。
それでも、ジェンダーレス制服の導入や、誰でも使用できるトイレの導入、性別欄を求めない履歴書を採用する企業の増加など、社会の空気は少しずつ変わってきています。
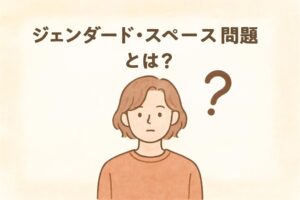
ノンバイナリーな私の体験談
私は生物学的には女性として生まれ育ちましたが、
幼いころからずっと「女の子らしさ」にモヤモヤを抱えてきました。
制服のスカートが嫌だったり、
「女の子なんだから〇〇しなさい」と言われると居心地が悪くなったり。
かといって、男の子になりたいわけでもない。
「自分が何者か」を説明できる言葉が見つからず、
長年その違和感を抱えたまま過ごしていました。
そんな私がノンバイナリーという言葉に出会ったのは、
双子の授乳を終えたタイミングでした。
「もう女性の体が必要なくなった。女性として生きることにも違和感がある。」
そう気づいたとき、調べて出てきたのが“ノンバイナリー”という概念だったのです。

初めて自分の感覚に名前がついたこと。
それは、大きな安心と自信につながりました。
今までのモヤモヤや葛藤に名前がつき、
「私だけじゃなかったんだ」と知ることができたのです。
ノンバイナリーの認知度と人口
近年、ノンバイナリーという言葉やその概念に対する認知は、少しずつ広まりつつあります。
アメリカのUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)による調査では、LGBTQ+に該当する成人のうち、約11%がノンバイナリーに該当すると報告されています。人数に換算するとおよそ120万人にも及び、決して少数とは言えない存在です。
また、Ipsos社が2023年に行った国際調査によると、世界27か国の平均で、全体の約1%がノンバイナリーやトランスジェンダー、または流動的な性自認を持っているとされています。このデータは、国や文化によって表現方法や受け入れられ方に差があるとはいえ、ノンバイナリーという存在が世界で認識されていることを示しています。
日本では公式な統計はありませんが、海外調査を人口比で当てはめると、
数十万人規模のノンバイナリー当事者がいる可能性があると考えられています。
出典: https://transequality.org/issues/resources/understanding-nonbinary-people-how-to-be-respectful-and-supportive
Ipsos Global Advisor | LGBT+ Pride 2023
ノンバイナリーと関連する他の言葉たち
ノンバイナリーという言葉を知ったとき、
「他にも似たような言葉があるけど、
何がどう違うの?」と感じたことはありませんか?
ここでは、
ノンバイナリーと並んで使われることの多い
関連用語を簡単に紹介します。
クィアとクエスチョニング
クィア(Queer)
もともとは侮蔑語として使われていた言葉ですが、現在では「性的指向や性自認において、既存の枠に収まらないあり方全般」を示す肯定的な言葉として使われています。
ノンバイナリーもクィアに含まれることがあります。

クエスチョニング(Questioning)
自分の性自認や性的指向についてまだ探っている段階のこと。
「何者かはまだわからない、でも探している」という状態にいる人を指します。

ジェンダーレス(Genderless)
性別にとらわれない考え方や表現スタイルを指します。ファッションやライフスタイルの文脈でもよく使われ、性自認ではなく「見せ方」のニュアンスが強い言葉です。
服装・髪型・商品カテゴリなどを「男女で分けない」外的・社会的な表現や思想のことなので、内面的な自認を表すXジェンダーやノンバイナリーと混同しないように注意が必要な言葉でもあります。
関連記事
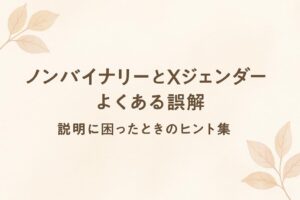


ノンバイナリーという言葉がくれたもの

私にとって、「ノンバイナリー」という言葉に出会えたことは、自分自身を認める大きなきっかけでした。
「女性じゃない。でも男性でもない。けど、私という存在は確かにここにいる。」
その実感が持てたことが、今の暮らしを支えてくれています。
あなたも、もし自分の性別に違和感があるなら、無理に答えを出さなくても大丈夫です。
モヤモヤしてもいい。言葉を探してもいい。
大切なのは、自分の感覚に耳をすませること。
あなたは、あなたのままでいい。