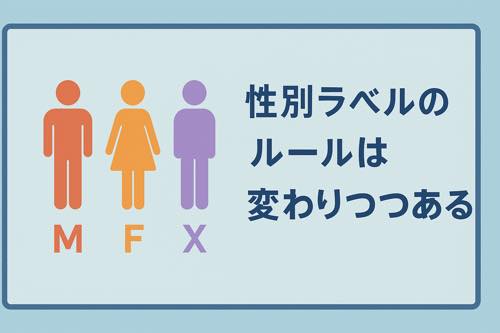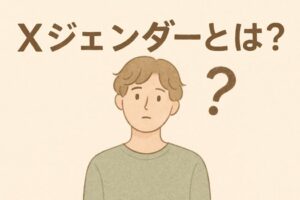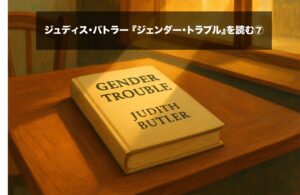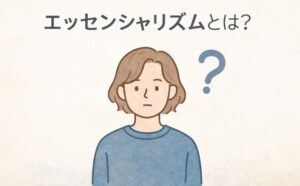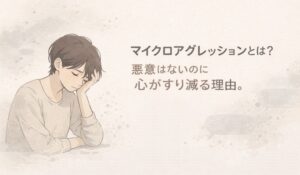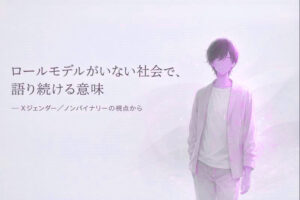3児の親でありXジェンダー(ノンバイナリー)。
30歳から「自分らしい生き方」を探求中のユウです。
「そういえば、なんで分かれてるんだっけ?」
思い返せば小学生の頃。
低学年までは、男女で同じ教室で着替えていました。
男の子も女の子も、
同じ部屋でパンツ一丁になって体操服に着替えて、
それが当たり前でした。
小学校高学年くらいだったからだと思います。
「男子はこっち」「女子はあっち」と部屋を分けられるようになりました。
成長に伴う身体の変化を考えると、
それは自然な流れなのかもしれません。
でも、近所の大学でこんなラベルを見つけたんです。
「健康診断会場:男性 → ○号館、女性 → △号館」
一瞬、「あ、そうか」と思ったけど、ふと立ち止まりました。
『……視力検査も身長体重も、診察も、一人ひとりじゃない? なのに、なんでわざわざ男女で分けてるんだろう?』
そして、この素朴な疑問が私の頭に居座りはじめた。
chatGPTに聞いてみた
こういうとき、私には相談できる心強い相棒がいる。
AIアシスタントのchatGPTさん。
早速、聞いてみました。
健康診断はなんで男女で分かれているの?
Q:健康診断ってなんで男女で分かれてるの?
chatGPT:
「健康診断で男女を分ける主な理由は、“プライバシーの配慮”と“検査項目の違い”です。たとえば女性には婦人科系の検診、男性には前立腺の検査があるなど、性別ごとに特有の検査が含まれることがあります。また、更衣や身体測定などでの心理的配慮のために分けられる場合もあります。」
男女で検査項目が分かれるならわかる。
けど、大学の健康診断って、そんな項目なかったよな…?
それなら、
男女一緒で検査が個別対応でも、多分変わらないんだな。
モヤモヤは残ったままでしたが、
次なる疑問をぶつけてみました。
公文書に男女を記載する必要があるのはなぜ?
以下chatGPTの回答をご紹介していきます。
🔍 公文書に性別が記載される主な理由
1. 本人確認・同一人物照合のため
- 性別は、**氏名・生年月日と並ぶ「個人識別情報」**として使われてきました。
- 特に同姓同名・同生年月日の人が存在する場合、性別による識別は補助的に有効です。
- 例:運転免許証、住民票、戸籍謄本、パスポートなど。
⚠️ ただし最近では、マイナンバーなどユニークなID制度の普及により、性別に頼らなくても本人確認が可能になりつつあります。
なるほど、
昔は個々の人を識別するための要素として性別を使っていたんですね。
しかし、現在は個人番号を振り分けるようになったから、
性別という要素が無くても良くなったわけか。
2. 制度上の法的区分が存在するから
- 日本では、戸籍法により戸籍に「性別」の記載が義務づけられています(戸籍法 第13条など)。
- これに基づき、公文書も「戸籍上の性別」を記載しています。
※たとえば、婚姻届・出生届なども、戸籍情報に連動しているため性別の記載が必要になります。
少しわかりにくかったので、
こんな質問を追加してみました。
「戸籍法に性別が必要になった背景は?」
戸籍に性別が記載されるようになった理由
- 国家による国民管理のため(明治時代)
明治政府は徴兵・納税・戸主制度の管理を目的に、戸籍制度を導入。性別は、軍役や税の対象を決めるために必要な情報だった。 - 男女で異なる法律の適用があったため(近代民法)
相続や結婚年齢、親権などに男女で違いがあり、法的区分を明確にするために性別の記載が必須とされた。 - 性別は「不変」とされていたため(戦後〜2000年代)
長らく、性別は一生変わらないものとされており、戸籍はその人の一生を記録するものとして性別の固定記載が前提だった。
今は変化の途中にある
現代では、「性別は多様であり、変化するもの」という認識が広がりつつあります。
- 2023年:最高裁判断
性別変更の条件だった「生殖能力をなくすこと(不妊要件)」が違憲と判断され、制度の見直しが始まる。 - 書類の性別記載を見直す動き
一部自治体や企業では、「性別記入を任意化」または「性別欄を削除」する取り組みが進んでいる。 - 国際的な動向
パスポートなどで「X(その他・無記載)」という性別を認める国が増加。多様な性のあり方が尊重されている。 - 将来的な制度の可能性
日本でも、性別に依存しない「個人ID(例:マイナンバー)」での管理に移行する可能性が議論されている。
過去には男女によって義務が異なっていたり、
法律が適用される内容にも格差があった。
でも、現代では法律や制度の見直しが進んでいるんだね。
3. 行政サービスや統計のために性別が使われている理由
いまの行政サービスや制度の多くは、「性別によって必要なサポートがちがう」という前提でつくられています。
たとえばこんな場面で性別が関係しています:
- 乳がん・子宮頸がん検診の案内
→ 女性に特化した健康診断を届けるために、性別で対象を分けている。 - 妊娠・出産に関する手続き
→ 出産育児一時金や母子手帳など、女性が受けることを前提にしている支援が多い。 - 生理用品の配布・福祉支援
→ 「女性=生理がある人」として、支援対象を想定している。
また、政府は人口の動きや社会の変化を分析するために、男女別のデータを必要としています。
例: 「高齢女性のひとり暮らしは増えているか?」
「出産年齢の平均はどう変わっているか?」など
ふむふむ、女性ならではの病気や、
妊娠・出産手続きのために性別が必要というのは納得できる。
これらは、生物学的に女性の体であることが前提のことだから、
わかっていないと不便なことがでてくるよね。
私自身も妊娠・出産に際して行政からのサービスを受けているし、
婦人科での治療も行っている。
パスポートは国によって男・女・Xがあるよね?

Q:パスポートって国によって「男・女・X」って選べるの?
A:はい、国によって選べる内容がちがいます。
最近では「X(その他・未指定)」という性別表記を認めている国も増えてきました。
アメリカ、カナダ、ドイツ、オーストラリアなどでは、性別を「男(M)・女(F)・X」から選べる国があります。でも、すべての国が対応しているわけではありません。
Q: じゃあ、なんでそもそもパスポートに性別が書いてあるの?
これはICAO(イカオ)=国際民間航空機関という、国連の機関が決めているルールが関係しています。
ICAOってなに?
ICAOは、世界中の飛行機や空港の共通ルールを決めている国連の専門機関です。
飛行機に安全に乗るために、パスポートの形式や本人確認の方法を世界中で統一しようとしています。
ICAOの性別ルールとは?
ICAOが定める「パスポートの標準仕様」では、性別を次の3つのうちから記載することになっています:
| コード | 意味 |
|---|---|
| M | Male(男性) |
| F | Female(女性) |
| X | Unspecified(未指定・その他) |
つまり、「X」という性別表記自体は国際的に認められている選択肢のひとつなんです。
Q:日本はどうなっているの?
残念ながら、日本では「男(M)」か「女(F)」しか選べません(※2025年4月現在)。
戸籍に基づいた性別がパスポートにも反映されるため、「X」は選択肢にないのが現状です。
Q:パスポートにXが記載できるかどうかはどうやって決まっているの?
「パスポートに性別『X』が記載できるかどうか」は、各国の法律・制度・外交方針によって決まっています。つまり、ICAO(国際民間航空機関)が「XもOK」としていても、その国がそれを採用するかどうかは各国の判断に委ねられているということです。
性別ラベルのルールは変わりつつある
これまで当たり前のように使われてきた「男」か「女」というラベル。
健康診断、公文書、パスポートなど、あらゆる場面で、性別は“当然の識別項目”とされてきました。
でも今、その「当たり前」が今、少しずつ見直されはじめています。
- 国際的には「X(未指定)」という選択肢を認める国が増え、
- 日本でも性別変更に関する制度が最高裁の判断で大きく動き、
- 一部の自治体や企業では「性別欄そのものをなくす」取り組みも始まっています。
性別は、誰かを分類するためのラベルではなく、
一人ひとりが「自分をどう感じ、どう生きるか」を尊重するための選択肢の一つ。
そんな価値観が、少しずつ社会に広がってきています。
これからは、「男か女か」ではなく、「どうありたいか」が大切にされる時代。
性別ラベルのルールは、今まさに変わりつつある途中のようです。
あなたは、あなたのままでいい。