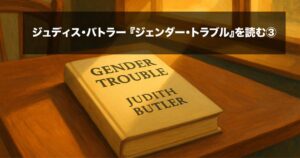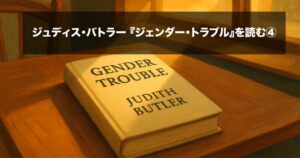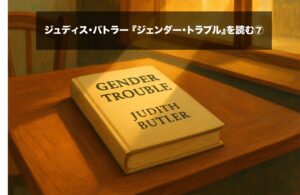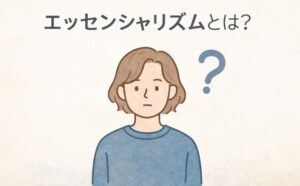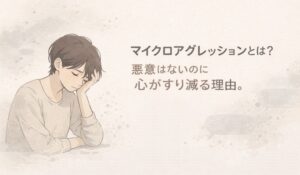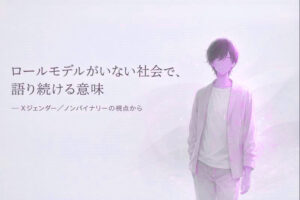「クエスチョニング」とは、自分の性的指向や性自認がまだ分からず、探している途中の状態を表す言葉です。
この言葉があることによって、自分の性のあり方について迷っていることを否定するのではなく、その過程自体を尊重できるようになります。
これまで社会は「男か女か」「異性愛か同性愛か」と二分法で語ることが多く、答えが出せない人は取り残されてきました。
たとえば、周囲が恋愛や結婚を当然のように語るなかで「自分は違う気がする」と感じていても、それを表現する言葉がなければ行き場のない不安や孤独を感じてしまいますよね。
クエスチョニングというラベルがあることで、「わからないままでもいいんだ」と安心できることもあるんです。
つまりクエスチョニングは、はっきりとした答えを持たないことも自分らしさの一部だと認めるための入り口となります。
「自分が何者なのかわからない」という方は、試しにセクシュアリティ診断を受けてみるのもおすすめです。
セクシュアリティ用語についてはこちらでまとめているので、興味がある方はあわせてどうぞ。

クエスチョニングの意味と定義
クエスチョニングは、自分の性的指向や性自認が「定まっていない」「決めていない」状態を意味します。
この定義が重要なのは、迷いが一時的でも長期的でも「存在していい状態」として認められる点にあります。
これまでは「どちらかに決めること」が前提とされ、曖昧さは受け入れられにくいものでした。
横浜市が発行するハンドブックにも「性的指向や性自認が決まっていない人」としてクエスチョニングが紹介されています[2]。行政の資料に載ることで、公的にも認知が進みつつあるのです。
「決めていないこと」を恥じたり、自分を責める必要はなく、その状態自体が一つのあり方であることがわかりますね。
参考資料
[2]横浜市「性的マイノリティの多様性ハンドブック」
クエスチョニング当事者が抱えやすい感情とその背景
クエスチョニングを自覚した人が抱きやすい感情の一つに「孤独感」があります。
社会では恋愛や結婚が当然視されているため、分からない自分を言葉にできず、不安や自己否定につながりやすいのです。
LGBT-JAPANのレポートでは「周囲に理解してもらえないのでは」「説明できない自分が悪いのでは」と悩む当事者の声が紹介されています[4]。
一方で、コミュニティや仲間との出会いを通じて「同じように迷っている人がいる」と知り、「自分は1人じゃなかった」と安心できたり、救われたと感じる人もいます。
同じ悩みを抱えている人たちに「クエスチョニング」というラベルがつくことで、つながるきっかけを得られる場合もあるのです。
参考資料
[4]LGBT-JAPAN「クエスチョニングとは」
海外におけるクエスチョニングを受け入れる動き
クエスチョニングを隠さずに語れる環境は、迷っている人が「自分も存在していい」と安心できるためにとても重要です。
海外では、そのための具体的な取り組みが広がっています。
アメリカの大学では、LGBTQセンター(大学や地域に設置される、性的マイノリティ(LGBTQ+)の学生や市民を支援するための拠点)が「Questioning students welcome(迷っている学生も歓迎)」と掲示し、クエスチョニングの学生が安心して集える場を提供しています。たとえば、Claremont CollegesのQueer Resource Centerは、迷いのある学生を含め、情報やカウンセリング、コミュニティ形成のサポートを行っています[5]。
さらに、GLSEN(Gay, Lesbian & Straight Education Network)が主催する「Day of Silence(沈黙の日)」は、1996年にバージニア大学の学生による授業プロジェクトとして始まりました。その後GLSENが支援を拡大し、現在ではアメリカ国内で数千校、世界60カ国以上の学校で行われています[6]。
この活動は、一日声を出さずに過ごすことで、『話せない人がいる』という現実を見える形にし、みんなが考えたり行動したりするきっかけにしているのです。
こうした国際的な活動は、クエスチョニングを含む、無理解や差別に苦しむ多様な立場の人たちを「見える存在」として社会に伝える大きな力になっています。
参考資料
[5]Claremont Colleges Queer Resource Center
[6]Wikipedia「Day of Silence」
日本でのクエスチョニングの広がり
日本でも少しずつ、クエスチョニングをはじめとした多様な立場の人たちが安心できる場所づくりが広がっています。
これは、当事者が「自分もいていい」と思える社会につながります。
まず、企業においては「アライ(ALLY)」の可視化が進んでいます。
LGBTQ+への理解と支援を明示する「アライ宣言」やステッカー掲示などを通じて、支援の意思表示を社会に広げる取り組みが生まれています[7]。
さらに、埼玉県では「アライチャレンジ企業登録制度」を整備し、県内企業の取り組みを可視化する仕組みも導入されています[8]。
また、NPO法人「虹色ダイバーシティ」は、LGBTQ+の実態に関する調査を定期的に行い、その結果を社会に発信しています。たとえば、性的少数者の割合や職場での課題などのデータは、政策づくりや理解を広げる根拠として活用されています[9]。
このように、日本でも多様な性のあり方を受け止めやすい土壌が育ち始めています。
参考資料
[7]株式会社アカルク「アライ(ALLY)の可視化取り組み」
[8]埼玉県「アライチャレンジ企業登録制度」
[9]虹色ダイバーシティ「LGBTQ調査研究・アドボカシー」
クエスチョニングとクィア(Queer)の違いと共通点
クエスチョニングとは
今はあえて答えを出さない「探している途中」の状態を表す言葉です。
自分の性的指向や性自認について、まだ確定していない、どちらとも決めたくないという内面的な揺らぎや過程を尊重し、肯定する言葉として使われます。
LGBTQIA+ Wikiでは、”Questioning is a term used to describe individuals who are exploring, learning, or experimenting with their sexual or romantic orientation, or gender identity”(クエスチョニングとは、自分の性的指向や恋愛指向、または性自認について、探求したり、学んだり、試したりしている人を表す言葉です)と定義されています[10]。
クィア(Queer)とは
クィアは、社会の決めつけやラベルから離れて、「自分はその枠には収まらない」と示す自己表現として使われる言葉です。
もともと “Queer” は英語で「変な」「奇妙な」という意味があり、LGBTQ+の人に対して侮辱的に使われてきました。けれども1980年代以降、LGBTQ+の運動やエイズ危機のなかで、当事者がこの言葉をあえて自分たちの言葉として使い直すようになりました。このように、差別語をポジティブな意味に変えて自分たちの力にすることを「リクレイム」と呼びます[11]。
クィアという言葉は、異性愛が「当たり前」とされる考え方や、「男性か女性か」という二つだけの分け方にとらわれません。つまり、「私はどの枠にも縛られない」という自己表現の方法になっています。
たとえば、アメリカで1990年代に生まれた活動団体 Queer Nation は、デモやイベントで “We’re here! We’re queer! Get used to it!”(ここにいるぞ!私たちはクィアだ!慣れろ!)と叫びました。これは「私たちは隠れないし、存在そのものが社会に対するメッセージだ」という強い意思表示でした。
さらに学問の分野でも「クィア理論」という研究が生まれました。これは「男と女の二分法」や「異性愛が当たり前」という社会の仕組みを批判的に見直し、もっと自由な生き方や多様性を考える学問です[12]。
クィア理論の出発点になったジュディス・バトラーの『Gender Trouble』を中学生でもわかるように解説するシリーズも書いていますので、興味がある方は合わせてどうぞ。
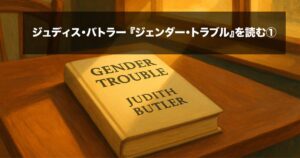
【クエスチョニングとクィアの違いのまとめ】
| 用語 | 意味・ニュアンス | 背景・位置づけ |
|---|---|---|
| クエスチョニング(Questioning) | 自分の感覚を探す「模索の状態」 | 個人の内省的プロセス、答えを急がない理解 |
| クィア(Queer) | 既存の枠に抵抗し、自分を自由に表現する言葉 | 政治的・文化的自己表明、学問(クィア理論)としても発展 |
【クエスチョニングとクィアに共通する精神 】
- どちらの言葉も、「男か女か」「異性を好きになるのが当たり前」といった決めつけにとらわれず、ゆらぎやあいまいさをそのまま大切にしています。
- また、はっきりしたラベルにしばられず、「自分は自分」と思える気持ちや、周りとどう関わるかを自由に選べる姿勢が共通しています。
参考資料
[10]LGBTQIA+ Wiki「Questioning」
[11]Wikipedia「Queer」
[12]Wikipedia「Queer theory」
青年期に多い自然な発達過程としてのクエスチョニング
「まだ分からない」と思う気持ちは、成長のごく自然な一部です。
中学生から高校生くらいの時期は、自分がどんな人なのかを考え始める大切な時期です。この時期には「自分は誰を好きになるんだろう?」「男らしさや女らしさって何だろう?」と迷うのは普通のことです。これは心や体が大人へ近づいていく中で、多くの人が経験する自然な過程です。
心理学者エリク・エリクソンは、この時期を「アイデンティティ(自分らしさ)を探す段階」と説明しました。アイデンティティとは「自分はどういう人か」という感覚のことです。彼の理論では、青年期は「自分らしさを見つける」か「役割が分からずに混乱する」かという課題に直面するとされ、迷うこと自体が成長の一部だと考えられています[13]。
また、最近の心理学の研究でも、思春期や青年期は「自分の価値観や将来像を試しながら、自分がどんな人なのかを探す」時期であると確認されています[14]。たとえば、高校生が「これは友情?それとも恋愛?」と考えることは、自然な探索の一例です。
大切なのは、周りの人が「まだ決めなくてもいいよ」と伝えることです。その一言で、本人は安心して自分の気持ちを探し続けられます。クエスチョニングは不安の証ではなく、「今の自分の感じ方をそのまま大切にできるラベル」です。
参考資料
[13]Wikipedia「Erikson’s stages of psychosocial development」
[14]Branje, S. et al., “Dynamics of Identity Development in Adolescence”, Frontiers in Psychology, 2021.
私自身の体験談:クエスチョニングという言葉に出会って
私も20代のころ、自分の恋愛感情が分からずに戸惑った経験があります。
性行為を前提とした男女の付き合い方に疑問を覚えつつも、何が嫌なのかうまく言葉にして説明することができずにいました。
友人や兄妹が話す恋愛話を聞きながら、自分はそのどこにも当てはまっていないような気がして、孤独を感じました。
30代になってから「クエスチョニング」という言葉に出会い、「迷っている状態も一つのあり方」と知ることができました。
今でも、自分の恋愛的な指向については「クエスチョニング」なままでいます。
でも、それが私なんだと思えたことで自分の抱えていた悩みも、個性の一つなんだと前向きに捉えられるようになりました。
この体験は「あいまいなの自分」を言葉の存在が、どれだけ大きな心の支えになるかを教えてくれました。
今後の社会で大切にしたいこと
これからの社会に必要なのは「まだ決めていない状態」をそのまま認めてくれる居場所です。
世の中にははっきりした答えを出せない/出さない人がいることを知ってもらって、その人たちが安心して暮らせる場所を増やしていくこと。
例えば、学校で「分からなくてもいい」と伝えること、職場で「クエスチョニング」という言葉を説明に含めること。
こうした小さな実践が、「クエスチョニング」な人の安心につながります。
海外の可視化の動きや日本の調査結果が示すように、社会全体で理解が広がりつつあります。
私は、誰もが「ありのままの自分」でいても大丈夫だと感じられる社会になってほしいと心から願っています。
クエスチョニング Q&A
Q1. クエスチョニングは一時的なもの?
一時的に名乗る人もいれば、一生そのままの人もいます。どちらも尊重されるべきあり方です。
Q2. 子どもが「クエスチョニングかも」と言ったら?
答えを急がせず「そう感じているんだね」と受け止めることが安心につながります。
Q3. LGBTQ+におけるQは?
クィアとクエスチョニングの両方を指す場合があります。文脈によって意味が変わることもあります。
Q4. クエスチョニングの人は支援を受けられる?
学校の相談窓口、地域団体、NPO法人などでクエスチョニングに関するイベントや支援を探せます。
私が運営しているオンラインコミュニティ「True Colors Lab」は、あなたをいつでも歓迎します^^
Q5. アセクシャルとの違いは?
クエスチョニングは「まだ分からない状態」、アセクシャルは「性的に惹かれにくい特性」です。
アセクシャルについてはこちらの記事でまとめています。

Q6. Xジェンダーとの違いは?
Xジェンダーは「男性でも女性でもない」あるいは「男性でも女性でもある」という性自認の人を指します。
Xジェンダーについては、こちらの記事でまとめています。
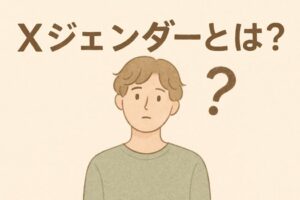
関連記事



どんな自分も「そのままで」価値がある
自分が何者なのか、決まっていないことや説明できないことを責める必要はありません。
まだ決められない、あるいはあえて決めないという気持ちも、「自分の一部」です。
揺らぎの中にいるあなたも、強く確信を持っているあなたも、どちらも尊い存在です。
社会の枠や周囲の期待に合わせる必要はなく、「今の自分の感じ方を大切にすること」が一番の力になります。
そして忘れないでください。
あなたは、あなたのままでいい。