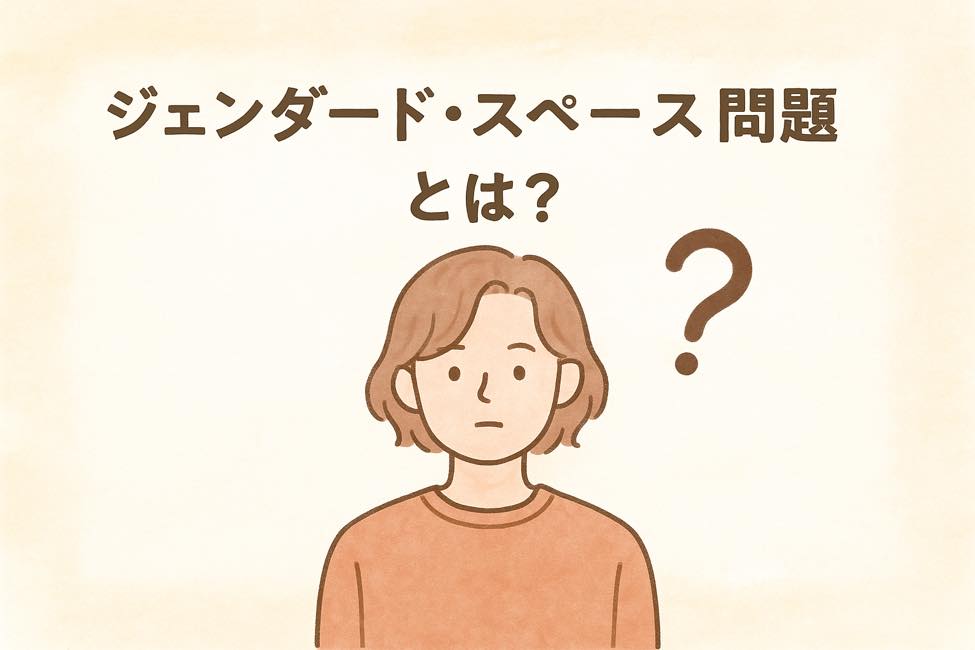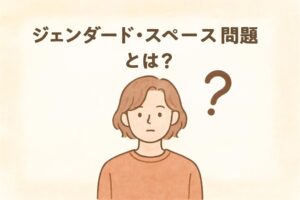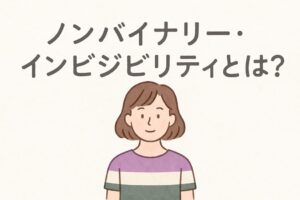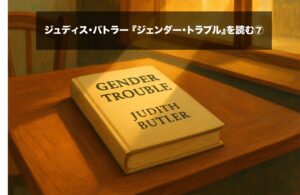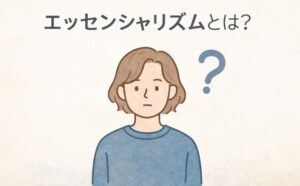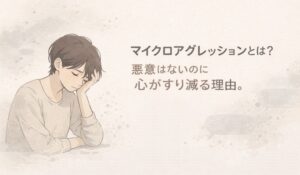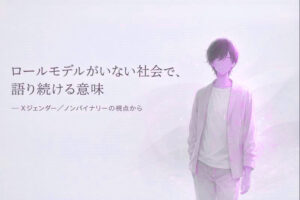ジェンダード・スペース問題とは、トイレや更衣室、大浴場などが「男性用」と「女性用」の二択を前提に作られていることによって、一部の人が安心して利用しにくくなる課題のことです。
とくに、性自認が「男性」「女性」のどちらかに当てはまらないノンバイナリーの人や、身体の特徴と自認する性別が一致しないトランスジェンダーの人の中には、このような空間を利用する際に不安や緊張を感じる人がいます。
たとえば、「自分はどちらを使えばいいのだろう」と迷ったり、周囲の視線を気にして落ち着けなかったりすることがあります。利用を避けてしまうと、健康や生活にも影響が出ることがあります。
この記事では、この「ジェンダード・スペース問題」がどういうものかを整理し、海外で広がるジェンダーニュートラルトイレの事例や、日本での現状を紹介しながら考えていきます。
ジェンダード・スペース問題とは?【定義と意味】
ジェンダード・スペース問題とは、トイレ・更衣室・大浴場などの空間が「男性用」と「女性用」の二択を前提に設計されていることによって、一部の人に利用上の不便や不安が生じる社会的な課題を指します。
特に、性自認が「男性」「女性」のどちらにも当てはまらないノンバイナリーの人や、身体の特徴と性自認が一致しないトランスジェンダーの人の中には、こうした空間を利用する際に次のような困難を感じる場合があります。
- 「どちらを選べばよいのか」と迷う
- 周囲からの視線や反応が気になる
- 不安から利用を避け、健康や生活に影響が出ることがある
すべての人が同じように感じるわけではありませんが、実際にそのような当事者の声が多数報告されていて、社会的に解決すべき課題として注目されています。
この問題を解決するために、ジェンダーニュートラルなデザインが求められているのです。
この問題は、当事者だけでなく、誰もが「性別に縛られない空間ってどんな形だろう」と考えるきっかけになると思います。ノンバイナリーって何?という方は、こちらの記事も合わせて読んでみてください。

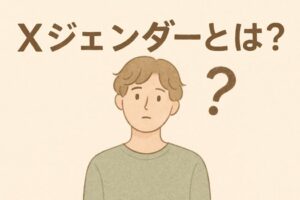
ジェンダーニュートラルとは?
「ジェンダーニュートラル」とは、男女のどちらかに限定しない考え方や仕組みを指します。
言葉で説明すると少し抽象的に聞こえますが、実際には次のような例があります。
ジェンダーニュートラルな言葉の使い方
「彼」「彼女」といった性別に結びついた呼び方ではなく中立的な表現を使うことができます。
日本語におけるジェンダーニュートラルな表現
日本語では、日常会話の中で性別に直結した言葉が多く使われています。
たとえば、「彼」「彼女」といった呼び方や、「お父さん」「お母さん」といった役割を性別で限定する言葉です。
これに対して、ジェンダーニュートラルな表現としては、たとえばこんな使い方がありますね。
- 「あの人」「その方」など、性別を限定しない人称
- 「親」「保護者」「パートナー」など、性別に依存しない呼び方
- 学校での呼びかけを「男子・女子」ではなく「みなさん」「生徒のみなさん」と呼ぶ
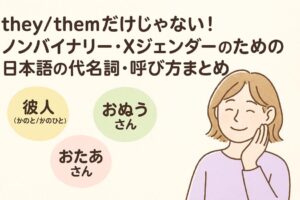
海外におけるジェンダーニュートラルな表現
英語圏では、性別を限定しない言葉の使い方がより広く浸透しています。
代表的なのは、人称代名詞 they/them です。性別がわからない人、あるいはノンバイナリーの人について話すときに、単数形としても「they」を用いることが一般的になってきました。
また、職業名や役職名でも変化があります。
- 「fireman(消防士・男性)」ではなく「firefighter」
- 「chairman(議長・男性)」ではなく「chairperson」
- 「stewardess(客室乗務員・女性)」ではなく「flight attendant」
こうしたジェンダーニュートラルな表現は、法律文書や学校教育、職場での公式文書にも広がっています。
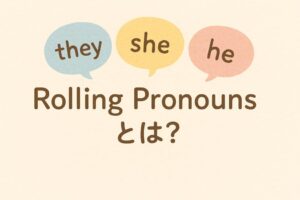
服装やデザインにおけるジェンダーニュートラルな例
日本での例
制服の自由化
近年、学校の制服を「男子=ズボン」「女子=スカート」と固定せず、スラックス・スカートを自由に選べる制度を導入する学校が増えています。ブレザー型の統一デザインを採用し、生徒が自分の希望で着用を選べるケースもあります。
企業ユニフォームの刷新
飲食店やホテル、航空会社などで、従業員がスカート・パンツを自由に選択できるユニフォームを導入する動きがあります。例として、日本航空(JAL)はCAの制服でスカート・パンツを選択制にしています。
日常のファッション
「メンズ」「レディース」と分けず、誰でも着られるサイズ展開やシンプルなデザインを打ち出すアパレルブランドも登場しています。ユニクロの「ジェンダーレスコレクション」やZARAの「Ungendered」ラインなどがその一例です。
海外での例
ジェンダーレスファッションブランド
ロンドンやニューヨークを拠点に、最初から性別を区切らない「ユニセックス」「ジェンダーレス」をコンセプトとするブランドもあります。たとえば、Telfar(テルファー)などがあります。
制服のジェンダーニュートラル化
イギリスの多くの学校では「全生徒がズボンもスカートも着用可能」とし、ニュージーランドでは性別に関わらず短パン・スカートの選択が自由化されています。
公共空間のデザイン
美術館や図書館などの職員制服、または病院の患者服などで「男女で色や形を分けない」デザインが採用される事例が増えています。
服装やデザイン
男女で分けないユニフォームや、誰でも着られるシンプルな服
施設の設計
トイレや更衣室を「男性用/女性用」だけでなく、誰でも利用できる形で整える
私はこの言葉を知ったとき、「ジェンダーにとらわれない=特別な人のためのもの」ではなく、誰にとっても安心できる仕組みなのだと理解しました。
ジェンダード・スペース問題を考えるうえで、ジェンダーニュートラルという言葉は切っても切り離せないものなのです。
海外のジェンダーニュートラルな取り組み
海外では「All-Gender Restroom(すべての人のためのトイレ)」の導入が進んでいます。
アメリカでは大学や空港を中心に性別を問わないトイレが設置されており、誰でも利用できることを示す「All-Gender Restroom」の表示が一般的になりつつあります。
また、カナダやヨーロッパの公共施設では、従来の男女を象徴するマークを使用せず、シンプルなアイコンや「Restroom」といった文字表記で示す事例が増えています。
こうしたジェンダーニュートラルなトイレは、ノンバイナリーやトランスジェンダーの人にとって利用しやすいだけでなく、子ども連れの親や介助が必要な人など、多様な利用者にとっても利便性が高いとされています。
日本の自治体・公共施設におけるジェンダーニュートラルな取り組み
豊川市(愛知県):学校での「みんなのトイレ」
愛知県豊川市の小学校・中学校では、性別を問わず使える「みんなのトイレ」が設置されています。共通の入口から複数の個室を利用できる設計で、児童からも「男女差を気にせず使える」と好意的に受け止められています。
参考:「みんなのトイレ」事例紹介
埼玉県:性の多様性を尊重した社会づくり条例と施設整備指針
埼玉県では2022年7月に「性の多様性を尊重した社会づくり条例」を施行しました。これに基づき、県有施設の新設や改修では「性別を問わず利用できるトイレや更衣室」を検討する方針が示されています。
参考:埼玉県公式サイト|性の多様性を尊重した社会づくり条例
埼玉県公式サイト|条例と施設整備に関するQ&A
登別市(北海道):新庁舎へのオールジェンダートイレ設置計画
北海道登別市では、2026年完成予定の新庁舎にオールジェンダートイレを設置する計画があります。近隣の室蘭市や伊達市でも同様の検討が進められています。
参考:登別市公式|新庁舎基本設計書(PDF)
ジェンダード・スペース問題がもたらす心理的負担と今後の課題
ジェンダード・スペース問題は、単なる「設備の不便さ」にとどまらず、心理的な負担につながることが指摘されています。
ノンバイナリーやトランスジェンダーの人の中には、トイレを利用する際に強い不安を感じたり、周囲の視線を意識して落ち着けなかったりする人がいます。調査や当事者の声では、次のような声を見つけました。
- 不安から長時間利用を我慢し、体調に影響が出た
- 利用中に視線や質問を受けるのではないかと常に緊張する
- 着替えの場が見つからず、学校や職場で困難を感じた
このような小さなストレスの積み重ねは、学校や職場への通学・通勤そのものを難しくする要因にもなり得ます。
私自身の体験から感じること
私自身、ノンバイナリーと自覚する前から、トイレや更衣室を使用する時に「自分はここを使っていいのだろうか」と不安に感じることがありました。
今でも、メンズルックの服を着ているときに女性用トイレを利用すると、周囲の視線を意識して落ち着けなかったり、声をかけられないかと不安になったりします。
一方で、多目的トイレを利用しようとすると、別の緊張が生まれます。
「車いすの方や、小さなお子さん連れの方が来たらどうしよう」と考えてしまい、自分がそこにいることに申し訳なさを感じるのです。
このように、どちらの選択肢を選んでも「安心して使える」という感覚が持ちにくいことが、私にとってストレスとなっています。
こうした体験は、ジェンダード・スペース問題が決して抽象的な話ではなく、日常生活に直接影響する現実であることを改めて実感させます。
関連記事


まとめ:ジェンダード・スペース問題は社会全体の課題
ジェンダード・スペース問題とは、トイレや更衣室などが「男性/女性」という二択を前提に設計されていることで、一部の人が安心して利用できない状況が生じる課題です。
この問題はノンバイナリーやトランスジェンダーの人だけに限らず、子ども連れの親や介助を必要とする人など、多様な利用者にも関わってきます。
そのため、従来の「男女二択の空間」を見直し、ジェンダーニュートラルなデザインを取り入れることは、誰もが安心して暮らせる社会づくりにつながると考えています。
誰もが安心して利用できる空間づくりが、これからも広まっていきますように。