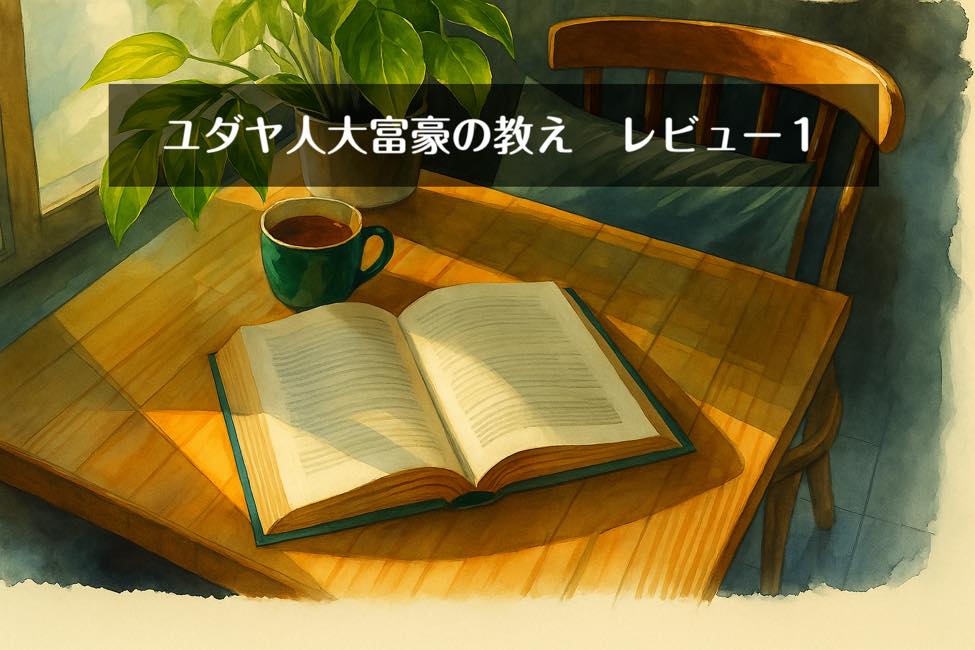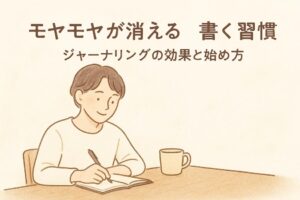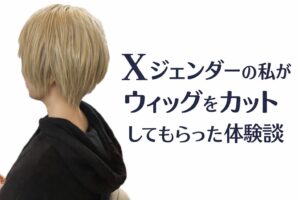本田健さんの『ユダヤ人大富豪の教え』を1/3ほど読み終えました。
刺さる言葉ばかりで、自分の中でも考えさせられることが多かったので、一旦感想をまとめてみます。
物事の本質を見抜く目を持つこと
「物事の本質を見抜く目を持つこと」。
これは、とあるテレビで「東大生とそうでない人の違いは何か?」という問いに対して、東大出身のタレントが言っていた言葉でもありました。そのときも「おお!」と思ったのですが、この本の中でも同じような考え方が登場していました。
では、その「本質を見抜く力」ってどうやったら養われるんだろう?
私は気になって、ChatGPTに聞いてみました。
提供したサービスの量と質=君が受け取る報酬額
私は今、情報発信の仕事をしていますが、これについてはいつも不安になります。
「自分が作っているサービスに、みんな本当に納得してくれているのかな?」と。
でも、継続してくださっている方がいるということは、何かしら気に入ってもらえているのかもしれません。
そこで、ふと思いました。
「どういうところが気に入っているか?」
この質問を、今まで一度もしてこなかったなと。
というわけで、早速コミュニティの方に質問してみることにします。
また、この話を読んで「多くの企業で働いている人は、自分がもらっている報酬が働きに見合っていると感じているのだろうか?」という疑問も浮かびました。
逆の立場で見れば、会社として社員にサービスに見合った報酬を出せているのだろうか?
もし出せないのであれば、その会社自体がうまくいっていない可能性もあるのかもしれません。
そう考えると、そこを見極められる「本質をみる目」も必要だと感じました。
夫がこれから転職するかもしれないので、ぜひ転職先の「本質」を見てほしいなと思います。
人は自分が好きなことをしている人間を応援したくなる
これは、とても素晴らしい考え方だと思いました。
サービスを提供する側としては「何か完成したものを提供しなきゃいけない」と思いがちです。
でも『100日後に死ぬワニ』のように、目標や目的がはっきりしているものは自然と応援したくなりますよね。
「発信の仕方」という視点で考えると、完璧なものを作ってから提供する必要はなくて、今の自分をそのまま出していくことも大切だなと感じました。
そして、みんなが応援したくなるような「夢」を自分の中で描けるようになりたい、と強く思いました。
好きなことを仕事にする
自分の「好きなこと」ってなんだろう?
本の中では「あたまでっかちなエリート」という表現が出てきた気がします。
それは「得意なことはよく把握しているけど、本当に好きなことがわかっていない」という意味でもあるのかなと感じました。
私自身も、これまでの人生で「他人から評価されること」ばかりを気にしてきて、本当に好きなものに目を向けられていなかったと気づきます。
このブログのテーマにもあるように、「かっこいい私」を目指す旅のためにも、好きなこと探しを毎日少しずつしていこうと思います。
誰に評価されるでもなく、時間を忘れて没頭できること。
それが何か、一緒に探してみませんか?