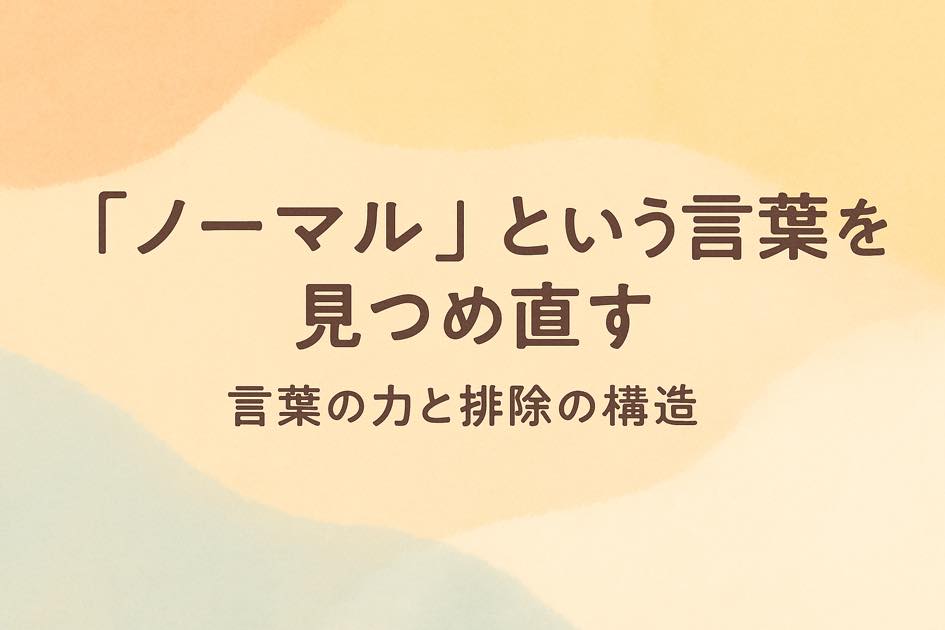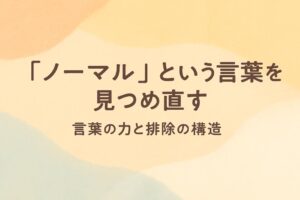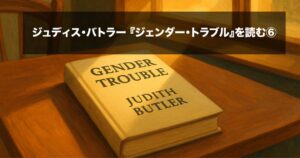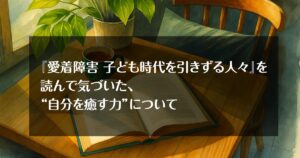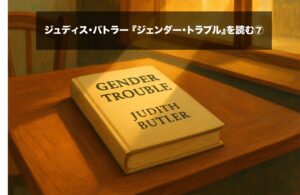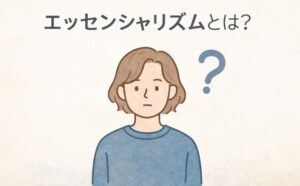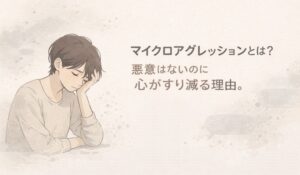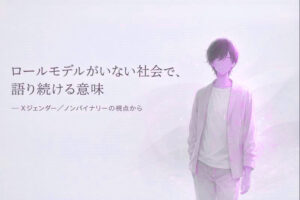「自分の恋愛はノーマルですよ」
ある日、LGBTQ当事者の若者が悩みを相談するテレビ番組で、MCの人がそう言いました。
その瞬間、胸の奥がざわざわしたんです。
私はそのMCさんと同じく無性(アセクシュアル)を自認しています。
だからこそ、「ノーマル」という一言が、なぜか心に引っかかりました。
たぶんそれは、“ノーマル”の裏側に“アブノーマル”という言葉が透けて見えたから。
誰かが「普通」と言うとき、そこには“普通ではない人”を自動的に生み出してしまう仕組みがあります。
そのことに気づいた瞬間、言葉の重さを改めて感じたのです。
私の体験:言葉が刺さった日と、自分を責めていた過去
以前、レズビアンの友人と話していたとき、私はこう言ってしまいました。
「私はノーマルじゃないから」。
すると友人は穏やかに、でも真っ直ぐにこう言いました。
「“ノーマル”って言うと、そうじゃない人を間接的に“アブノーマル”と言っていることになるから、気をつけたほうがいい。」
その言葉を言われたときは、とてもショックでした。
私は自分のことを”普通じゃない”と思い込み、無意識のうちに自分を卑下していたことに気づいたのです。
あの瞬間、「自分をこれ以上、言葉で侮辱しないであげて」と言われたような気がしました。
それ以来、私は”ノーマル”や”普通”という表現に””をつけて考えるようになりました。
テレビで聞いた「私はノーマルですよ」への違和感
ある夜、若者のLGBTQ当事者たちが恋愛や生き方の悩みを語るテレビ番組を観ていました。
MCの人は自分を「無性」と語りながら、「私の恋愛はノーマルですよ」と言って話を始めたのです。
話の内容は「恋愛は会ってすぐにアリ・ナシが決まる」「嫉妬したら恋をしている」のようなことだったと思います。
私は「ノーマル」という言葉を聞いた瞬間、胸の奥に複雑な感情が渦巻きました。
“なぜ自分の恋愛観をノーマルだと断言できるのだろう?”
“自分の恋愛観以外をアブノーマルと間接的に言ってしまってることに気づいてるのかな?”
しかも、この番組の相談者は、「恋愛という感覚がわからないけど、一度は恋愛してみたい」というお悩みを寄せていたんです。
恋愛の形は人それぞれ。
「ノーマル」と言った瞬間、その人にとっての“普通”が、他の誰かの“異常”を作り出してしまうことがあるのです。
私はハラハラしながら成り行きを見守っていました。
きっと悪意があるわけではないのでしょうが、言葉の構造がそうさせてしまうのです。
その夜、私は改めて「自分が無意識に使ってきた言葉」について想いを巡らせたのでした。
“ノーマル”という言葉の中にある構造的な壁
“ノーマル(normal)”という言葉は、本来「基準」「標準的な状態」という意味を持ちます。
一見、無害な言葉に見えても、それは「基準を決める行為」でもあります。
つまり、「外れる人」を同時に生み出すのです[1]。
心理学ではこれを二項対立構造(にこうたいりつこうぞう)と呼びます。
たとえば、「正常/異常」「男/女」「健常/障害」。
社会が作り出した“基準のペア”は、見えない線を引く働きをします。
でも現実には、人のあり方はそのどちらにも完全には当てはまりません。
性のあり方も恋愛の形も、グラデーション(連続的な幅)を持っています。
“ノーマル”という言葉は、その多様性の幅を削ぎ落としてしまう危うさを含んでいるのです。
[1]Florence Ashley『Queering Our Vocabulary』(2022)
言葉が無意識にもたらす線引き:フレーミング効果と“空気”
心理学では、「フレーミング効果」という考え方があります。
これは、言い方を変えるだけで、人の受け取り方や判断が変わる現象のことです。
たとえば、ある人が次のように言ったとします。
- 「彼は普通の恋愛をしている」
- 「彼は自分らしい恋愛をしている」
この2つの文は、どちらも事実を述べているように見えます。
でも、“普通”という言葉が入ることで、無意識のうちに「普通ではない恋愛」や「基準から外れた人」が存在するという前提が作られます。
つまり、「どう表現するか」が、聞き手の中に“線引き”を生んでしまうのです。
もう少し身近な例を挙げましょう。
たとえば、ニュースでこんな言葉を耳にしたとします。
- 「同性婚を認めると、普通の家族の形が崩れる」
この言い方には、“普通の家族”というフレーム(枠)が隠れています。
「普通の家族」とは何か、「崩れる」とはどういうことか――
そこに、聞き手の価値観や偏見が自動的に入り込むのです。
実際、心理実験でも、「成功率80%」と「失敗率20%」という2つの表現を提示すると、
同じ内容でも「成功率80%」と聞いた人の方がポジティブに判断する傾向があると示されています[2]。
これがフレーミング効果です。
言葉は、事実そのものよりも“見え方”を変える。
だからこそ、“普通”や“ノーマル”という枠を無意識に使うと、
「そこから外れた人たち」を“違う”と感じさせてしまうのです。
また、アッシュという心理学者の同調実験(1951)では、
人は周囲が間違っていても、7割以上の人が“空気に合わせる”ことが明らかになりました[3]。
つまり、“みんなが普通と言っている空気”の中では、自分の感覚を隠してしまう人が増えるのです。
“普通”という言葉は、たった一語で社会の“空気”を作る。
だからこそ、私たちはその言葉が誰を前提にしているのか、少し立ち止まって考える必要があります。
[2]McLeod, S. (2023). Framing Effect. Simply Psychology.
[3]Tutor2u – Conformity: Asch (1951)
メディアも注目する「ノーマル」発言のリスク
近年、メディアや教育現場では「ノーマル」「普通」という言葉の使い方に注意が促されています。
特定非営利活動法人・LGBTとアライのための法律家ネットワークが発行した
『LGBTQメディア・ガイドライン(第2版)』にはこう記されています。
自分の性のあり方を基準にしないようにしましょう。例えば「(LGBTQ ではない)ふつうの人」「ノーマルな人」という表現や同性愛を「禁断の愛」と表現する等、異常・異質なものとして位置付けないよう注意しましょう。
[4]。
また、アメリカ心理学会(APA)の“Avoiding Heterosexual Bias in Language”では、性的関係や惹かれに関して「すべての人が異性愛者である」「異性愛が標準的である」と仮定することを避けるよう明言されています[5]。
言葉を変えることは、ただの言い換えではなく、“誰を想定するか”を変えること。
それがインクルーシブ(包摂的)な社会の第一歩です。
[4]LGBTとアライのための法律家ネットワーク『LGBTQメディア・ガイドライン(第2版)』
[5]APA『Avoiding Heterosexual Bias in Language』
クィアという言葉
「クィア(Queer)」という言葉は、もともと英語で「奇妙な」「変わっている」という意味を持っていました。
一時期は侮蔑的な言葉として使われていましたが、90年代以降、LGBTQ+コミュニティの中で自らの多様性を誇る言葉として再定義されました。
今では、性的指向や性自認にとどまらず、“社会が決めた枠の外で生きること”全般を肯定する立場としても使われます。
クィアという考え方は、「ノーマル」と「異常」という線引きをなくし、
「そもそも“普通”って誰が決めたの?」という問いを私たちに投げかけます。
この視点は、性の話だけではなく、
生き方・働き方・恋愛・家族・身体など、
あらゆる「普通」とされる基準を見直すヒントになります。
クィアについてはこちらの記事にまとめています。

「ノーマル」を使わないための言葉選び
「ノーマル」と言わずに話すのは難しそうに思えるかもしれません。
でも、ちょっとした工夫で、相手を傷つけない言い方に変えられます。
主語を「自分」に置き換える
・「普通の恋愛」→「自分の恋愛の形」
・「普通のカップル」→「私たちの関係」
・「普通はこうする」→「私はこう感じる」
“普通”という言葉には“基準”が含まれます。
主語を「自分」に変えるだけで、相手を否定しない表現にできます。
包摂性を意識した言葉選び例
| 従来の表現 | 言い換え例 |
|---|---|
| ノーマルな恋愛 | 自分の恋愛観・恋愛のタイプ |
| 普通のカップル | いろんな形のカップル・この二人 |
| 異常な関係 | 特徴のある関係・特別な関係 |
| 男/女らしい | その人らしい |
| 普通の人 | (具体的な形で)〇〇な人 |
誰かを排除しない言葉を一緒に探そう
“ノーマル”という言葉を使う人の多くは、悪意があるわけではなく、
ただ、他の言い方を知らないだけだと思います。
だからこそ、知ることが大切。
言葉を学び、考え続けることが、誰かを思う優しさにつながるんじゃないでしょうか。
あなたは、あなたのままでいい。