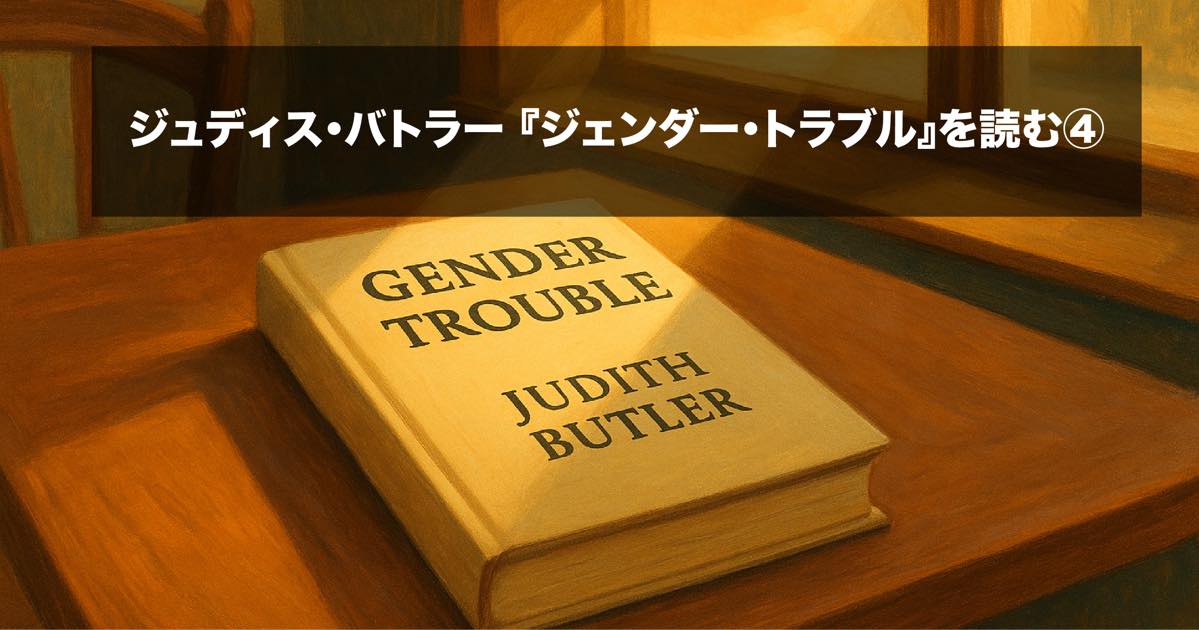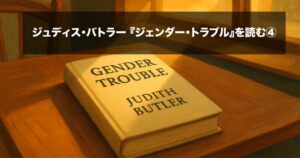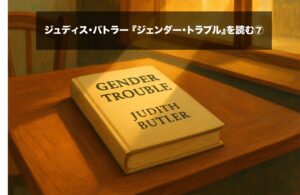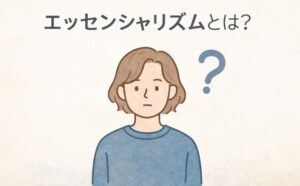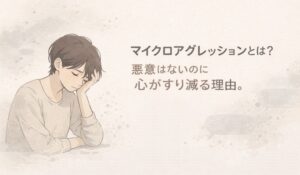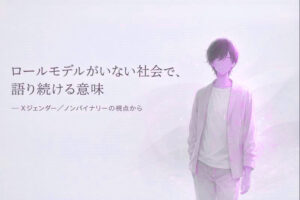世界のフェミニズムやクィア理論を語るときに、必ず名前が出る名著——ジュディス・バトラーの 『ジェンダー・トラブル(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)』。
「ジェンダーは生まれつきではなく“演じられるもの”だ」という衝撃のアイデアを提示し、フェミニズム理論の歴史を大きく塗り替えた一冊です。いまや世界中の大学で必読文献とされ、出版から30年以上たった今でも引用され続けています。
そんなとんでもなくすごい本が、オープンアクセスで誰でも無料で読めるのです。
しかし、実際にページを開いてみると、「英語」「哲学用語だらけ」「とにかく難しい」という三重苦。
そこで私は決めました。ChatGPTに“中学生でもわかるように”かみくだいてもらいながら、この本を少しずつ読み進め、解説していこうと。
このシリーズでは、フェミニズムやクィア理論について知識0の筆者が、難解な議論を肩ひじ張らずに解説しつつ、私自身の「なるほど!」「ここわからん!」といったリアルな反応も残していきます。
名著を一緒に探検するような気分で、ゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。
前回までの内容はこちらです。
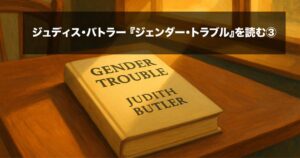
今日は第1章の「iv. Theorizing the Binary, the Unitary, and Beyond」のパートについてchatGPTに解説してもらいました。
フェミニズムも「ひとつの答え」にまとめすぎると危険
フェミニズムの議論は、すべてを「ひとつの敵」「ひとつの答え」にまとめようとすると危険です。
なぜなら「女性を抑圧するのは男性中心主義だけだ」と言い切ってしまうと、逆にその単純な図式に縛られてしまい、他の差別や不平等が見えなくなるからです。
たとえば「女性差別をなくす」と言っても、同じ女性の中でも状況は違います。裕福な家庭に育った女性と、経済的に苦しい家庭に育った女性とでは経験する困難はまったく異なりますし、白人女性と有色人種の女性が受ける差別も違います。もし「敵は男だけ」と考えてしまうと、こうした複雑な背景を無視してしまい、かえって一部の女性の声しか拾えなくなってしまうのです。
つまり、フェミニズムは「敵はひとつ」と決めつけるのではなく、差別や抑圧が重なり合う複雑さを理解しようとすることが大切です。
「女性」という言葉もひとまとめにはできない
「女性」という言葉を、ひとつのまとまった集団だと考えることはできません。
なぜなら「女性」と言っても、その中には人種、階級、年齢、性的指向、障害の有無など、さまざまな違いがあるからです。
たとえば日本で「女性の働きやすさ」を考えるとき、正社員としてフルタイムで働く女性と、非正規雇用でパートやアルバイトをしている女性では必要な支援が違います。さらに、子育て中のシングルマザーと独身女性では直面する課題も異なります。にもかかわらず「女性はこうだ」と一括りにしてしまうと、多くの人が置き去りになります。
だから「女性」というカテゴリーを固定的に考えるのではなく、常に多様な声や経験が交わる場としてとらえることが必要です。
矛盾を抱えたままでも連帯できる
女性たちの間には意見の違いや矛盾があって当たり前です。それでも、矛盾を抱えたままでも連帯して行動することはできます。
なぜなら「みんなで完全に同じ意見になること」が前提になってしまうと、少数派の声が無視されたり、「全員一致」という言葉で妥協を強いられたりするからです。
たとえば学校の文化祭で出し物を決めるとき、全員が納得するアイデアが出るまで話し合いを続けていたら、なかなか先に進めません。でも「意見は違うけれど、この部分は一緒にやろう」と決めれば行動できます。フェミニズムの連帯も同じで、完全な一致を目指す必要はなく、違いを残したままでも共に進むことができるのです。
つまり「矛盾や違いを残したままでも行動できる」という発想こそが、より柔軟で現実的な連帯を生み出します。
「女性」という言葉は常に未完成だからこそ意味がある
「女性」という言葉は、完成された一枚岩の定義ではなく、常に変化し続ける未完成なものです。
なぜなら、その言葉の意味は時代や社会の中で何度も作り直されてきたからです。
たとえば戦後の日本では「女性=専業主婦」というイメージが強くありました。しかし現代では「働く女性」「政治に参加する女性」「子どもを持たない女性」といった多様なあり方が広く認められるようになっています。さらに世界を見れば、国や地域によって「女性らしさ」の意味も大きく違います。
つまり「女性」という言葉は常に争われ、変化し続けてきたのです。その未完成さは弱点ではなく、むしろ新しい意味や可能性を生み出し続ける強みだと言えます。
アイデンティティは行動の中でつくられる
アイデンティティは、最初から決まっている固定的な属性ではありません。行動や実践の中で立ち上がり、また変わっていくものです。
なぜなら、あらかじめ「あなたはこういう人だ」と決めつけられると、新しい生き方や可能性が閉ざされてしまうからです。
たとえば「女の子だから理系は向いていない」と言われたら、本当は理科や数学が得意でも、その可能性を伸ばす機会を失ってしまいます。でも実際には、勉強や仕事、活動を通して自分のあり方は変化します。その中で新しいアイデンティティが立ち上がり、また別の形に変わっていくのです。
だからアイデンティティは「生まれつき与えられるもの」ではなく、「経験や行動の中で一時的に形を持ち、また変わるもの」だと考えることが、より現実的で自由な生き方を可能にします。
感想
さて、ここで一息。
今回は原文訳がとても難解だったので、chatGPTに中学生バージョンをつくてもらっても無理なんじゃ…と恐れていましたが、思ったよりずっと、わかりやすい解説を作ることができてほっとしています。
今回のテーマは、Xジェンダー/ノンバイナリーの私も自分ごととして捉えやすい部分がありました。
特に、「アイデンティティは行動の中でつくられる」という部分では、
アイデンティティは「生まれつき与えられるもの」ではなく、「経験や行動の中で一時的に形を持ち、また変わるもの」と説明しています。
私はまさにこれを、自分の人生で体験してきました。
生まれたときのアイデンティティは「女性」でしたが、自分の恋愛経験や性自認に悩んだ経験を経て、どんどん変わっていきました。そして今ではXジェンダー/ノンバイナリーというアイデンティティを持っています。
今となっては、「女性」と思っていたアイデンティティは、外の世界から刷り込まれてきたアイデンティティだとわかります。でも、それを受け入れていた幼少期があり、そこから思春期を経て変化していったのです。そして、これからの人生で自分のアイデンティティが全く変化しないという保証もありません。
これらのことは、すべて経験とそれに基づく自分の行動によって形作られてきたものだと思います。
さて、次回はどんな展開が待っているんでしょうか。
お楽しみに。