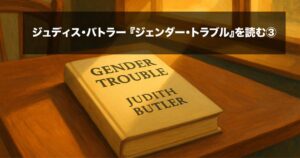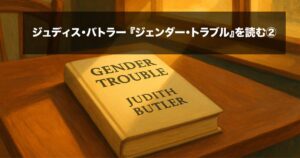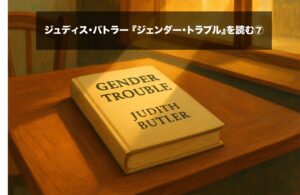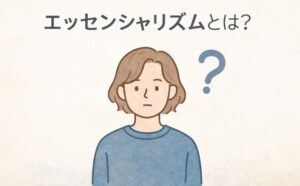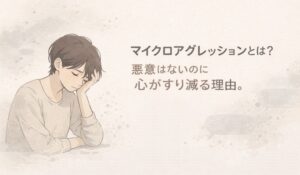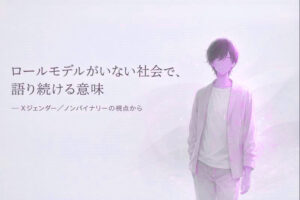世界のフェミニズムやクィア理論を語るときに、必ず名前が出る名著——ジュディス・バトラーの 『ジェンダー・トラブル(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)』。
「ジェンダーは生まれつきではなく“演じられるもの”だ」という衝撃のアイデアを提示し、フェミニズム理論の歴史を大きく塗り替えた一冊です。いまや世界中の大学で必読文献とされ、出版から30年以上たった今でも引用され続けています。
そんなとんでもなくすごい本が、オープンアクセスで誰でも無料で読めるのです。
しかし、実際にページを開いてみると、「英語」「哲学用語だらけ」「とにかく難しい」という三重苦。
そこで私は決めました。ChatGPTに“中学生でもわかるように”かみくだいてもらいながら、この本を少しずつ読み進め、自分の感想や気づきも交えて記録していこうと。
このシリーズでは、フェミニズムやクィア理論について知識0の筆者が、難解な議論を肩ひじ張らずに解説しつつ、私自身の「なるほど!」「ここわからん!」といったリアルな反応も残していきます。
名著を一緒に探検するような気分で、ゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。
今日は第1章の「ⅡI. Gender: The Circular Ruins of Contemporary Debate」のパートについてchatGPTに解説してもらいました。
ジェンダーは生まれつきではなく“つくられる”
ジェンダーは、生まれつき自然に決まるものではなく、社会の中で“つくられる”と考えられます。
なぜなら、「男らしさ」「女らしさ」というイメージは国や文化によって違い、時代とともに変わるからです。
たとえば、昔は「男は働く人・女は家庭に入る人」とされていましたが、今では多くの国で女性も社会で働くことが当たり前になっています。逆に男性が育休を取るのも自然なことになりつつあります。
つまり、“男だからこう”“女だからこう”というのは自然に決まっているのではなく、社会がつくったルールにすぎないのです。
ボーヴォワール:「女に生まれるのではなく、女になる」
シモーヌ・ド・ボーヴォワールは「人は女として生まれるのではなく、女になるのだ」と語りました。
これは大切な視点で、女性として生きることは体の特徴で自動的に決まるのではなく、社会からの期待やしつけによって“女らしさ”を身につけさせられる、という意味です。
たとえば、小さい頃から「女の子なんだからスカートを着なさい」とか「おしとやかにしなさい」と言われる経験があります。そうした文化的な圧力が積み重なって「女になる」のです。
つまり、ボーヴォワールは「女らしさ」は自然なものではなく、社会から“ならされる”結果だと考えました。
🖋 人物解説
シモーヌ・ド・ボーヴォワール(Simone de Beauvoir, 1908–1986)
フランスの哲学者・作家。代表作『第二の性』(1949)は「第二波フェミニズム」の出発点となった名著で、女性の生き方を哲学的に問い直しました。
イリガライ:「女性は一つの型に収まらない」
リュス・イリガライは「女性は一つの性ではない」と主張しました。
彼女がそう言うのは、社会の言葉やルール自体が男性を基準につくられていて、その中で女性は「男の反対側にいる存在」「欠けた存在」として描かれてしまうからです。
たとえば、日本では仕事を語るときに「男の正社員」「女のパートタイマー」と言うことがあります。これは「正社員=男」「パート=女」という思い込みが社会に根強いからです。実際には女性の正社員も男性のパートもいるのに、あえて性別をつけて呼ぶことで「男=本業を担う人」「女=補助的に働く人」というイメージを強めてしまいます。
イリガライは、こうした男性を基準にした枠組みそのものを問い直しました。女性は「男性の反対としての女性」ではなく、それぞれに異なる経験や価値をもつ多様な存在だと考えたのです。彼女が目指したのは、女性を“男性の影の存在”としてではなく、独自の言葉と視点を持つ主体として認めることでした。
🖋 人物解説
リュス・イリガライ(Luce Irigaray, 1930– )
ベルギー出身の哲学者・精神分析家・フェミニスト理論家。著書『この性はひとつではない(Ce sexe qui n’en est pas un, 1977)』で、女性を「ひとつではない性」と捉え、男性中心の思想を根本から批判しました。
ⅡI. Gender: The Circular Ruins of Contemporary Debateのまとめ
シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、社会の中で女性が「性に結びついた存在」とされてしまうことを批判しました。けれど彼女の議論は、結局「女性は性である」という前提をある程度受け入れた上でのものでした。
リュス・イリガライはここを逆転させます。彼女は「女性は性である」という見方そのものが、実は男性中心の言語が作り出した幻想だと批判したのです。つまり、「女性は性に縛られている存在」なのではなく、「女性をそう定義する言葉のほうが、男性を基準にした仕組みの一部」だというのです。
この逆転によって、女性は「性そのもの」ではなく、むしろ男性的な言葉に覆い隠され、多様な姿を持つ存在として見直す必要がある、とイリガライは示しました。
性とジェンダーの考え方はどう変わってきた?
性やジェンダーの考え方は、時代ごとに大きく変わってきました。流れをざっくり追ってみましょう。
17世紀(デカルトなど)
「心と体」を分ける考え方(心身二元論)が広まる。
→ 理性的な“心”が高く評価され、感情や肉体は低く見られる。
→ この価値観が「理性的=男性/肉体的=女性」というイメージと結びつく。
19〜20世紀前半(生物学的決定論)
「卵子をつくるのが女、精子をつくるのが男」といった体の役割で性を固定。
→ 「生物学が運命」という考え方が支配的になる。
1949年:シモーヌ・ド・ボーヴォワール
『第二の性』を発表し、「人は女に生まれるのではなく、女になる」と提唱。
→ 性は生まれつきではなく、社会や文化によって“つくられる”という考えが広まる。
1970年代後半:リュス・イリガライ
『この性はひとつではない(1977)』で、「女性は男性の反対ではなく、多様な存在」と論じる。
→ 男性中心の言語や思想を根本から批判し、女性を独自の存在としてとらえ直そうとした。
1990年:ジュディス・バトラー
『ジェンダー・トラブル』を刊行。「“自然な性”すら社会が作ったものかもしれない」と提案。
→ 性とジェンダーの区別そのものを揺さぶり、二分法を超える視点を提示。
こうした流れを経て、現在では「性やジェンダーは固定されたものではなく、多様で変化するもの」という考えが世界的に広がっています。
つまり、今私たちがジェンダーを語るときには、この長い歴史の積み重ねの上に立っているのです。
男女二元論の歴史の流れで見る
1. 古代社会以前(多様な性の認識もあった時代)
- 一部の地域(例:古代メソポタミアやインドのヒジュラ、北米先住民のツー・スピリット)では、男/女以外の性役割が文化的に認められていた。
- 男女二元論はまだ絶対的ではなく、複数の性や役割が共存していた。
2. 古代ギリシャ・ローマ(紀元前5世紀頃〜)
- プラトン(前427–前347):理性を魂に、感情や欲望を身体に結びつけ、男性を理性、女性を身体に重ね合わせた。
- アリストテレス(前384–前322):女性を「不完全な男性」と位置づけ、男を基準として女を劣った存在とみなした。
→この頃に「男=完全/理性」「女=不完全/身体」とする二元的で序列的な考え方が強まった。
3. 中世キリスト教社会(5〜15世紀)
- 聖書の「アダムの肋骨からイヴが生まれた」という物語が、女=男から派生した存在という理解に利用された。
- 教会法や神学によって「女は男に従うべき」という秩序が社会に広まった。
→ 男女二元論が宗教的な正当化を与えられ、「神が定めた秩序」とされた。
4. 近代哲学(17世紀〜)
- デカルト(1596–1650):心身二元論を提唱。理性(心)と肉体(体)を分け、理性=普遍/身体=制御されるものとした。
- この枠組みの中で「理性的=男性/身体的=女性」というイメージが結びつき、文化と自然、主体と客体の対立に男女が重ねられた。
→男女二元論が哲学的に強固に支えられた時代。
5. 近代科学(18〜19世紀)
- 解剖学や医学が発展し、「男女は根本的に異なる生物学的存在」と説明されるようになる。
- 18世紀以前:ヨーロッパには「一性モデル」という考え方があり、女性は「未発達の男性」と見なされていた(ラ・クール=ヘルミ『Making Sex』参照)。
- 18〜19世紀以降:「二性モデル」が定着。男性と女性は根本的に異なる存在であり、身体や生殖器によって明確に分けられるとされるようになった。
→この頃から「男女二元論=科学的事実」として信じられるようになる。
6. 20世紀以降
- ボーヴォワール(1949):『第二の性』で「人は女に生まれるのではなく、女になる」と述べ、ジェンダーの社会的構築性を提唱。
- イリガライ(1977):『この性はひとつではない』で、女性は男性の“反対”ではなく、多様で表象しきれない存在だと主張。
- バトラー(1990):『ジェンダー・トラブル』で、セックス自体も社会が構築するものであり「自然にある」わけではないと論じる。
→これまで「自然」とされてきた二元論そのものが揺さぶられる。
まとめ
- 古代以前:複数の性のあり方が共存。
- 古代ギリシャ〜中世:哲学や宗教が「男/女」の二分法を強化。
- 近代:哲学と科学が二元論を「普遍的で自然なもの」と位置づける。
- 20世紀以降:フェミニズムとクィア理論が「二元論は社会が作ったもの」と批判・解体。
感想
今回は、「わかりやすい説明をchatGPTにしてもらうこと」に、とても苦労した回でした。
それが、内容を見ていただいたらわかるんじゃないかと思います。
なぜ、大変なのかといえば、私には西洋哲学やフェミニズムの歴史の背景知識が何もないので、そもそも「男性・女性の二元論」や「性の捉え方(セックス/ジェンダー)」がどういう歴史をたどってきたのかについて、わからないからです。
そんなわけで、今回は本文に書いてあった内容以上に、歴史的な背景の補足をchatGPTにお願いすることにしました。
これまでの性とジェンダーに関わる捉え方の歴史を見てみると、男女の二元論が約2400年も!「当たり前」と考えられていたということがわかりますね。そりゃあ、この根深い歴史を動かすのは大変だ。
面白いと思ったのは、宗教、哲学、科学など色々な分野の研究家たちが、みんなそれぞれに「男女のあり方」についてずーっと議論をしていた、ということです。
そのくらい、シンプルには切り分けられない様々な要素があったり、差別や格差があったり、そういう歴史の中で「うまく分類しよう」としてきた。そして、その破壊を試みたのがバトラーというわけですね。そう思うと、とても痛快です。
次回もお楽しみに。