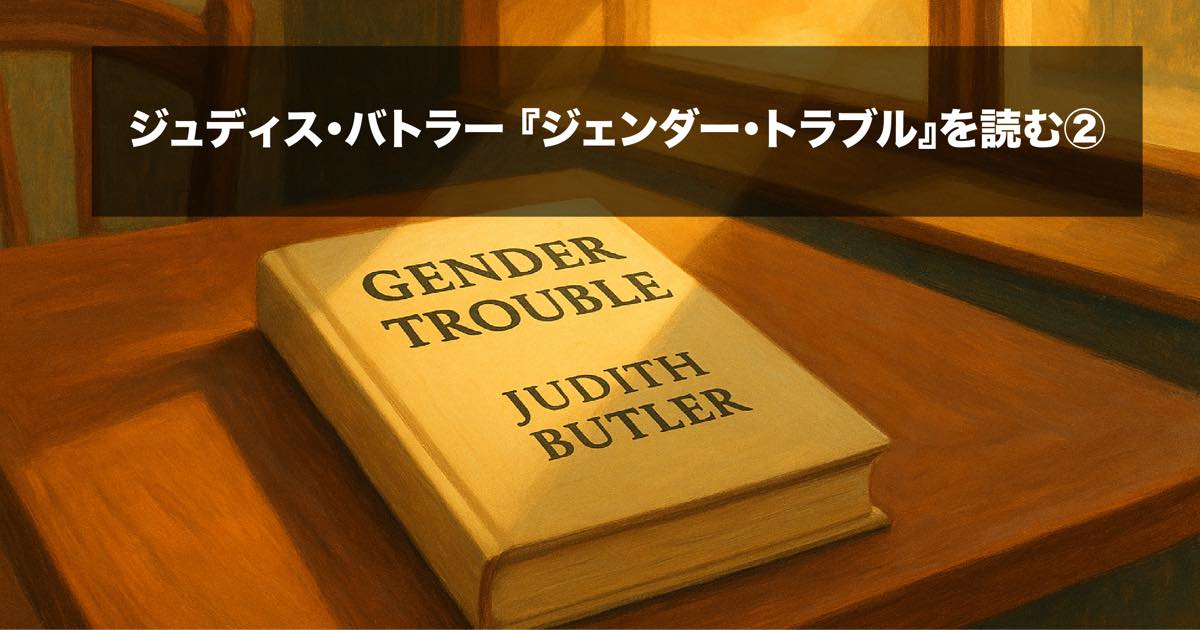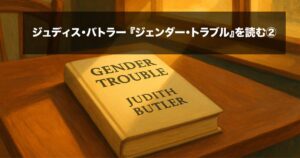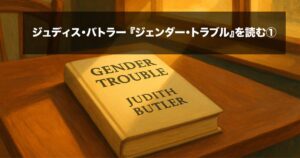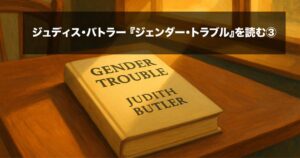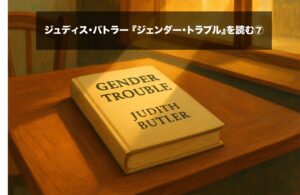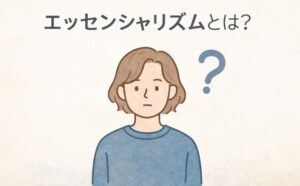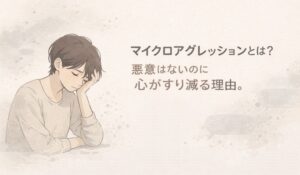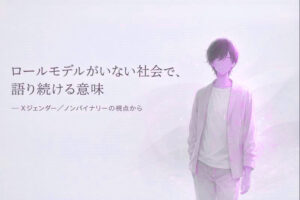世界のフェミニズムやクィア理論を語るときに、必ず名前が出る名著——ジュディス・バトラーの 『ジェンダー・トラブル(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)』。
「ジェンダーは生まれつきではなく“演じられるもの”だ」という衝撃のアイデアを提示し、フェミニズム理論の歴史を大きく塗り替えた一冊です。いまや世界中の大学で必読文献とされ、出版から30年以上たった今でも引用され続けています。
そんなとんでもなくすごい本が、オープンアクセスで誰でも無料で読めるのです。
しかし、実際にページを開いてみると、「英語」「哲学用語だらけ」「とにかく難しい」という三重苦。
そこで私は決めました。ChatGPTに“中学生でもわかるように”かみくだいてもらいながら、この本を少しずつ読み進め、自分の感想や気づきも交えて記録していこうと。
このシリーズでは、フェミニズムやクィア理論について知識0の筆者が、難解な議論を肩ひじ張らずに解説しつつ、私自身の「なるほど!」「ここわからん!」といったリアルな反応も残していきます。
名著を一緒に探検するような気分で、ゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。
今日は第1章の「Ⅱ. The compulsory order of sex/gender/desire」のパートについてchatGPTに解説してもらいました。
1. 性(sex)とジェンダー(gender)の区別が崩れる
本文訳
「もし“セックス”の不変性が疑われるなら、この“セックス”という構築は、ジェンダーと同じく文化的に作られたものかもしれない。むしろセックスは常にすでにジェンダーだったのかもしれない。」
解説
従来は
- セックス(sex=身体的な性別。男か女かを体で分けること) は自然に決まるもの
- ジェンダー(gender=社会的・文化的に作られる役割やイメージ。男らしさ・女らしさなど) は社会が後から意味をつけるもの
と説明されてきました。
※以降「セックス」と「ジェンダー」はこの定義のもと話がすすみます。
でもバトラーは、この区別自体を揺さぶります。
つまり「自然に決まると思われていた、男か女かを体の特徴で分けることもまた、社会が作った枠組みかもしれない」と問いかけているのです。
具体例
赤ちゃんの性別判定
出産時、医師は赤ちゃんの外性器を見て「男の子」「女の子」と記録します。でもこれは“自然に二つあるから”ではなく、社会が「二つに分けるルール」を作っているから可能になっているのです。
インターセックスの存在
体の特徴が「男/女」の二分法に当てはまらない人は少なくありません。それでも社会や法律は「どちらかに決めろ」と強制してきました。
科学の定義の変化
昔は「卵子を作るのが女、精子を作るのが男」と定義されました。やがて「XXとXYの染色体」が基準になり、さらにホルモンや脳の働きが持ち出されるようになりました。もしセックスが絶対に自然で不変なら、定義がこんなに揺れるはずはありません。
2. 「自然に決まるセックス」というのは見せかけ
本文引用(訳)
「ジェンダーは、セックスという“自然なもの”を前提に意味を加えるのではなく、むしろ“自然なセックスが存在する”という見え方そのものを作り出す装置である。」
解説
普通なら、「セックス(sex=身体的な性別。生まれつき男か女か)」が自然に存在していて、その後に社会が「男らしさ」「女らしさ」という意味(=ジェンダー)を上乗せする、と考えがちです。
けれどバトラーは、それ自体が逆だと指摘します。
ここでいう “自然なセックス” とは、「生まれつき体によって二種類に分かれるもの(男と女)は、文化の前から自然に存在しているはずだ」という考えのことです。
バトラーは、この「もともと自然にあるはず」という見え方こそが、実は社会によって作られているのだ、と言うのです。
つまり、ジェンダーという社会的な仕組みが、『男と女の二つしかないのが自然』だと私たちに思わせている。
たとえば、トイレのマークが「青いズボン=男性」「赤いスカート=女性」と描かれていると、それが当然の区別に思えてきますよね。
でも実際には、その色や服装の選び方は社会が決めたルールであって、生まれつき自然なわけではありません。
それなのに「自然に男と女は分かれている」と信じ込んでしまう。
この「自然に見える仕組み」こそが、バトラーの言うジェンダーなのです。
具体例:スポーツのルール
スポーツの世界を見てみましょう。
- バレーボールでは、男子のネットは高く、女子は低く設定されています。
- 陸上競技では、女子のハードルは男子より低くなっています。
こうした区別は「体の自然な違いがそのまま反映されたもの」だと感じがちです。
でも実際には、人間が「男はこう」「女はこう」という制度を作ったから存在している違いです。
私たちはその制度を見て、「やっぱり男女は違う」と思い込みます。
ここに、「自然な違い」に見せかけられている構造があります。
3. まとめ
- 「男/女」という体の区分(セックス)すら、自然なものではなく社会が作った枠組みかもしれない。
- その枠組みを「自然にある」と信じ込ませる仕組みがジェンダーである。
- だから「セックス=自然、ジェンダー=文化」という分け方は成立しない。
感想:じゃあ結局「自然な状態」ってなんなんだろう?
ここで私自身がどうしても気になったのは、「じゃあ自然な状態って何?」 という問いです。
体には確かに筋力や体格の違いがあります。
けれど、それを「男/女」という二つの箱に分け、制度やルールに落とし込むのは人間が決めた社会のルールかもしれない。
そこまではわかった。
でもだとすれば、「自然」と「文化」の境界はどこにあるのでしょうか。
むしろ、人間が解釈しているものはすべて「自然」ではない、
バトラーは、その点を私たちに考えさせようとしているのではないか、そう感じました。