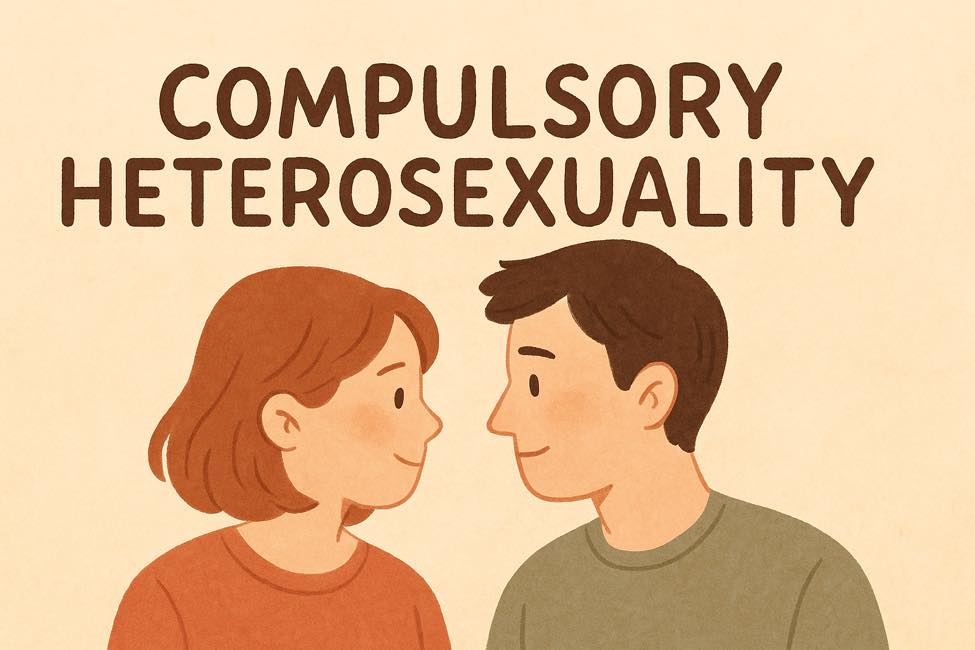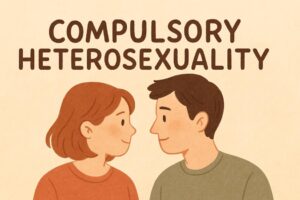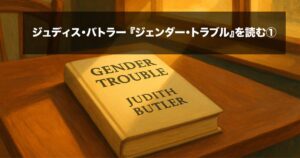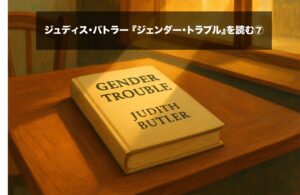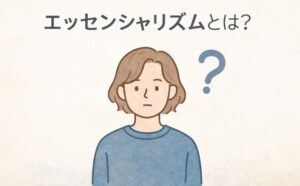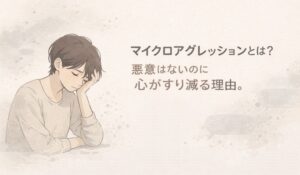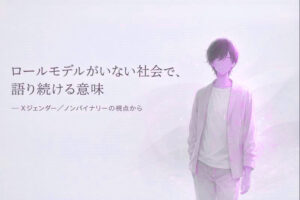「彼氏/彼女はいるの?」
「そろそろ結婚は?」
こんなことを言われたことはありませんか。
一見すると当たり前の会話に思えるかもしれませんが、その言葉の奥にはCompulsory Heterosexuality(コンパルソリー・ヘテロセクシュアリティ/強制的異性愛)という社会の仕組みが隠れています。
Compulsory Heterosexualityとは、「恋愛や結婚は男女の間だけで成立するものだ」と社会が当然の前提として扱い、それ以外の関係を受け入れにくくしてしまうことを意味します。
1980年にフェミニスト(女性の立場から社会を考える人)のアドリエンヌ・リッチ(Adrienne Rich)が論文「Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence」の中で提案した考え方です。
この仕組みの中では、同性を好きになる人や、恋愛にあまり関心がない人、そしてノンバイナリー(男女のどちらかに当てはまらない性のあり方)の人などが、自分の気持ちや存在が社会から尊重されていないと感じることもあります。
例えば、学校の劇やダンスで必ず男女のペアを組まされること。
ドラマや映画で登場する恋愛がほとんど男女カップルばかりであること。
会社の制度が異性同士の結婚だけを前提に作られていること。
こうした日常の小さな出来事の積み重ねによって、異性愛以外の生き方や関係性は社会の中で見えにくくなってしまいます。
この記事では、この考え方の定義や背景、海外と日本での事例、そして私自身の体験を紹介しながら、この問題について一緒に考えていきたいと思います。
Compulsory Heterosexualityとは?定義と背景
Compulsory Heterosexuality(コンパルソリー・ヘテロセクシュアリティ/強制的異性愛) という言葉は、英語の2つの単語からできています。
- Compulsory(コンパルソリー) …「強制される」「仕方なく従わされる」という意味
- Heterosexuality(ヘテロセクシュアリティ) …「異性愛」、つまり男女のあいだの恋愛や結婚を指す言葉
この2つを合わせると、「異性愛を強制すること」「異性愛が当然だとされる仕組み」という意味になります。
この考え方は1980年、アメリカのフェミニストであるアドリエンヌ・リッチ(Adrienne Rich)が発表した論文「Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence」で広まりました[1]。
リッチは「異性愛が自然で普通だとされることで、女性が男性に頼らざるを得ない社会の構造が強化されている」と指摘しました。
たとえば「結婚して子どもを持つのが当たり前」と語られることや、「恋愛は男女で行うもの」と描かれる物語は、他の生き方や関係の形を社会の中で見えにくくしてしまいます。
つまり、Compulsory Heterosexualityとは「異性愛が唯一の自然な生き方」とされる社会的な仕組みを指すのです。
参考資料
[1]Adrienne Rich, Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence (1980)
海外で広がったCompulsory Heterosexualityの考え方
海外では、この考え方に基づいた議論や社会の変化が進んでいます。
異性愛だけを当然とする考えを疑い、多様な生き方を見えるようにする取り組みが行われてきました。
例えば、アメリカやカナダでは、学校教育の中で「家族や恋愛の形はいろいろある」と教える授業が始まっています。
これにより、子どもたちは「恋愛は男女だけではない」と自然に理解できるようになります。
また、同性婚の合法化は「結婚は男女に限られる」という社会のルールを大きく変えるものでした。
さらに哲学者ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル』(1990年)で「性やジェンダーは生まれつきではなく社会が作り出すものだ」と述べ、Compulsory Heterosexualityの議論をさらに広げました[2]。
つまり、海外では教育・制度・学問のすべてにおいて、異性愛しかないという考えを揺さぶる動きが続いているのです。
参考資料
[2]Judith Butler, Gender Trouble (1990)
Compulsory Heterosexualityを変える、海外での教育や制度の取り組み
リッチやバトラーの議論を背景に、海外では少しずつ社会の仕組みが変わってきました。
特に、教育の場や法律の制度に多様な恋愛や家族の形が取り入れられるようになっています。
学校教育での変化:多様な家族や恋愛の形を教える
アメリカやカナダ、ヨーロッパなどでは、学校教育の中で「家族や恋愛にはいろいろな形がある」と伝える取り組みが広がっています。
イングランドでは、小中学校でLGBTQ+を理解できる授業が義務化されました[3]。同性カップルや多様な家族の形が教材に登場し、子どもたちが自然に多様性を学べるようになっています。
また、スコットランドはLGBTQ+の歴史を学ぶことを学校教育に義務づけた世界初の国です[4]。専用教材も用意され、性的マイノリティに関する理解を深める授業が行われています。
こうした教育の変化は、「恋愛や家族は男女のもの」という思い込みを和らげ、異性愛以外の関係性も子どもたちにとって自然なものとして伝わるきっかけになっています。
参考資料
[3]England Now Mandates LGBTQ+ Sex Ed. Why Doesn’t America?
[4]Scotland Is Now the First Country to Require LGBTQ+ History in Schools
法律や制度の変化:同性婚の合法化と法的保障
法律や制度の面でも大きな変化がありました。
2001年にオランダが世界で初めて同性婚を合法化しました[5]。その後、カナダ(2005年)、スペイン(2005年)、南アフリカ(2006年)、ノルウェーやスウェーデン(2009年)、フランスやニュージーランド(2013年)、そしてアメリカ(2015年)など、多くの国へと広がりました[6][7]。
さらに最近では、ギリシャが正教会の影響が強い国としては初めて同性婚を合法化しました。
ギリシャは国民の大多数がギリシャ正教徒であり、正教会は長い間、社会や政治に強い影響を与えてきました。
特に「結婚は男女の結びつき」「家族は父母と子で構成される」という考え方を当然のものとし、同性婚には一貫して反対してきました。
また、中絶についても「命は受胎の瞬間から神聖」とする立場から否定的であり、家族観においても男女の役割分担を重視する価値観を広めてきました[1]。
そのため、こうした背景を持つギリシャで同性婚が合法化されたことは、単なる制度の変更ではなく、社会の根本的な価値観に大きな変化が起きた象徴的な出来事といえます。
参考資料
[1]BBC News, Greece legalises same-sex marriage in historic reform (2024年2月16日)
https://www.bbc.com/news/world-europe-68315207
こうした法律や制度の変化は、異性愛以外の愛や家族の形が「当たり前の選択肢の一つ」として認められる大きなステップとなっています。
参考資料
[5]LGBTIQ Family Recognition Milestones Since 1990: A Comprehensive Global Timeline
[6]Timeline of Same-Sex Marriage Laws
[7]21 Other Countries Where Same-Sex Marriage Is Legal Nationwide
[8]Greece legalises same sex marriage in landmark change
社会全体への広がり
これらの取り組みは「恋愛や結婚は男女の間で行うもの」という強い前提を少しずつ変化させています。
同性婚の合法化や多様性教育の導入によって、異性愛だけが唯一の選択肢ではないことが、社会全体で認められる方向へ進んでいるのです。
Compulsory Heterosexualityを変える、日本での取り組み
日本でも、「恋愛や結婚は男女が前提」という考え方は少しずつ変わり、制度や教育にも新しい動きが出てきました。
2015年、東京都渋谷区は同性カップルに「パートナーシップ証明書」を発行する制度を開始しました。
これにより、病院での付き添いの配慮や公営住宅の申込みなど、生活の一部で関係性が認められる場面が増えました[9]。
その後、制度は多くの自治体へ広がり、2025年時点で日本の人口の約9割超が暮らす自治体で同様の制度が利用できる状況になっています[10]。
教育では、2017年の検定を経た中学校の道徳教科書の一部に、初めて性の多様性に関する内容が盛り込まれるようになりました。その後、小学校の保健や道徳の教科書でも、性の多様性に触れる記述が増えています[11]。
参考資料
[9]渋谷区「パートナーシップ証明 発行の手引き」
[10]朝日新聞デジタル「同性カップル制度、人口カバー率93%」
[11]松尾由希子「小・中・高の教科書にみる性の多様性の記載」
Compulsory Heterosexualityの体験談
私自身も、恋愛や結婚は男女でするものだという空気に違和感を持ってきました。
職場の人から「彼氏できた?」と聞かれて答えに困り、適当に誤魔化したことがあります。
親戚から「結婚はしないのか、子どもはまだか」と言われることにプレッシャーを感じたこともありました。
特に世代が上の人たちから、「男性との結婚や子どもを産むことが女性として当然の役割」として話されることに対して、違和感がありました。
社会に合わせようとごまかしたりしているうちに、「自分の方がおかしいのではないか」と思い込もうとしたこともありました。
今思えば、こうした経験こそがCompulsory Heterosexualityの影響だと思います。
何気ない会話や空気の中に「異性愛が当たり前」という前提が潜んでいて、自分の気持ちを表に出しにくくさせていたのです。
私には3人子どもがいるので、「家族のかたち」について一緒に考える時には、多様な家族のあり方を一緒に学びたいなと思います。
関連記事
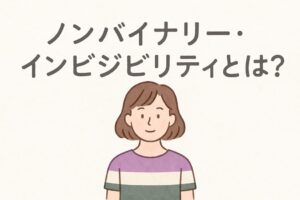


まとめ
・Compulsory Heterosexualityは「恋愛や結婚は男女のもの」と前提にする仕組みのこと
・そのため異性愛以外の生き方や性のあり方が見えにくくなる
・海外では教育や制度の変化、日本でも小さな取り組みが始まっている
ここまでをふまえて、私は「多様な生き方が自然に受け入れられる社会」に近づいてほしいと感じます。
あなたは、あなたのままでいい。