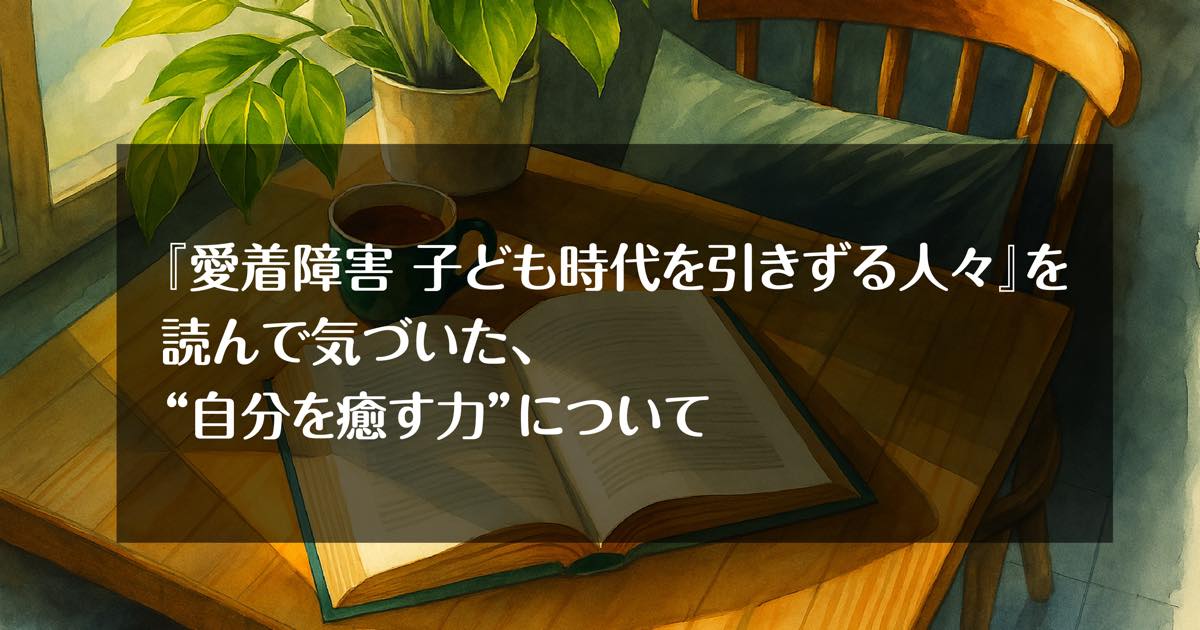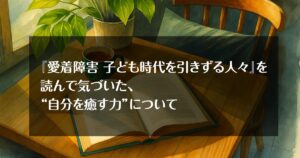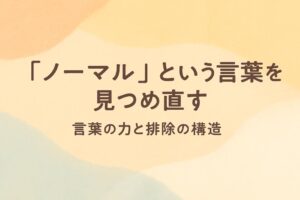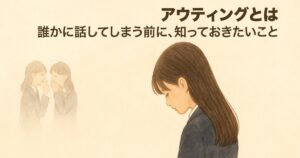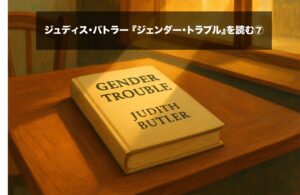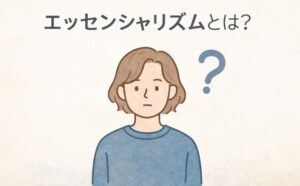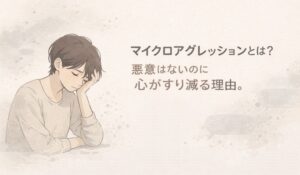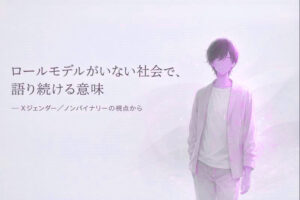※本記事にはプロモーション(アフィリエイトリンク)が含まれています
愛着障害って、知っていますか?
子どもの頃に、親や身近な大人との関係の中で“安心できるつながり”を十分に感じられないまま育つと、大人になってからも人との関わりが少し難しく感じることがあります。
それを心理学では「愛着障害(あいちゃくしょうがい)」と呼びます。
難しく聞こえますが、つまり「人を信じることが怖い」「頼るのが苦手」「自分には価値がない気がする」——そんな心のクセのことです。
この言葉は、私が抱えているパートナーとの関係性について改善していくために、心理学的なアプローチや実践的なアプローチを模索する中でたまたま知りました。
私は幼い頃、父の怒鳴り声や「しつけ」という名の暴力が日常の中にありました。
その経験から、「誰にも頼れない」「怒られないように頑張らなきゃ」と思いながら大人になりました。
本の中で紹介されていた「回避型」という愛着の傾向を読んだとき、心理学的なテストでいうと、自分はこれに当てはまるんだろうなと思いました。
けれど、読んでいて感じたのは、生涯愛着障害を抱えて苦しんできた人たちのエピソードと今の私には違いがありそうだ、ということでした。
私はこのブログを通じて、「自分自身を受け入れていく」ことによって、“誰かに癒してもらう”のではなく、“自分で自分を認めていくこと”ができるようになってきたのです。
この本は、そんな「自分で自分を癒す力」が私に備わってきていることを気づかせてくれた一冊でした。
愛着障害とは何か
「愛着」とは、人と人とのあいだに生まれる“心のつながり”のことです。
赤ちゃんが泣いたとき、親があやしてくれる。
怖いとき、抱きしめてくれる。そんな安心感の積み重ねが「愛着」をつくります。
しかし、その安心が得られず、いつも怯えたり、拒絶されたりして育つと、心の中に「どうせ誰も助けてくれない」という思いが残ってしまうことがあります。
それが「愛着障害(attachment disorder)」と呼ばれる状態です。
岡田尊司さんは本書の中では、大人の愛着のタイプを大きく3つに分けています。
・安定型:人を信頼し、助けを求められるタイプ
・回避型:人に頼らず、自分の中に閉じこもるタイプ
・不安型:相手の反応に過敏になり、過剰に不安を抱くタイプ
どれも「生き延びるための心の工夫」であって、悪いものではありません。
ただ、子ども時代の防衛パターンが大人になっても続くと、対人関係や自己肯定感に影響してしまう――それが“愛着を引きずる”ということなんです。
「これは自分のことだ」と感じた瞬間
読んでいて最も印象に残ったのは、「自立とは、周囲に認められ受け入れられる過程であり、同時にそうした自分に対して“これでいいんだ”と納得する過程でもある」という一節でした。
私は創作活動を止められない性格で、いつも何かを創っていたいとう欲があります。
それは、歌であったり、ピアノであったり、ハンドメイドの作品であったりしました。
そういうこれまでの活動について、読んでいてふと、「ああ、私は“安全基地”を探していたのかもしれない」と気づきました。
自分が否定されない場所、好きなことをそのまま表現できる場所。
それが、私にとっての「安全基地=創作」だったんです。
幼少期の体験と“回避型”の自覚
本を読み進める中で、私は自分が「回避型」の傾向があると気づきました。
思い返せば、幼い頃の私は父の怒鳴り声が怖くて仕方なかった。
叩かれたり、理不尽に責められたりしても、母は守ってくれなかった。
だから、「この家ではそういうものなんだ」と思うしかなかった。
中学生になって身体的な暴力は減っても、父からの言葉の暴力は続きました。
「私だったらこんなの簡単に解けた」「ピアノなんて弾けても意味がない。勉強しろ。」
そんな言葉の一つひとつが、心の奥に傷を残していきました。
その結果、私は「誰かに頼る」ということが極端に苦手になりました。
本当に限界まで追い詰められないと、助けを求めることができない。
愛着の回避傾向とはまさにそのことなんだと、本を通じて初めて言語化できました。
今では、自分の父を恨んだりする気持ちはもうなくなりました。
それは私自身が、自分を守ってくれた「心の癖」に気づき、手放し始めたからだと思います。
そして、自分が親になった今、当時の父母の仕事の状況を考え、いかに子育てが大変だったか、その中で頑張ろうとしてくれていたのかがわかるからです。
父母が苦労をしながらここまで育ててくれたことにも、心の癖があったおかげで手に入れた創造性にも、今は感謝の気持ちでいっぱいです。
発信と自己回復のプロセス
私が「30からのRe:Startブログ」を始めたのは、同じように悩んでいる人の力になりたかったからです。
最初は心理学的なことを書くつもりはありませんでした。
でも、ブログやメルマガを読んでくれる方、コミュニティのメンバーからの話を聞く中で、その多くが人間関係や生きづらさに悩んでいると知り、自然と心のテーマを扱うようになりました。
発信を続けるうちに、私は自分のセクシュアリティと本気で向き合うようになりました。
それは「自分で自分を許す」作業でもありました。
これまでタブーのように思っていた“自分が幸せになること”を、ようやく目指せるようになったのです。
本田健さんや、情報発信のメンターとの出会いも大きな転機でした。
人との温かい関わりを通じて、「他人と関わっても大丈夫」という新しい信頼感が少しずつ芽生えていきました。
創作は「自由」と「解放」の象徴
最近では、「なりたい自分」を語ったり、エッセイを出版したりと、以前の自分では考えられなかったことに挑戦しています。
否定されるのが怖くて何も言えなかった頃とは違い、今は「自由」に表現できる。
この感覚こそ、愛着障害を自分で克服するための一つのかたちなのだと思います。
創作を通して、自分の声を自分で受け止められるようになった。
それはきっと、外の世界に頼らずとも、自分の中に安全な場所をつくれるようになったということです。
本を読んで見えた「自分で自分を癒せる」という希望
読みながら何度も思いました。
学生時代の自分がこの本を読んでいたら、テストの結果はきっと“レッドゾーン”だったと思う。
でも、今の私は専門知識がなくても、自分で少しずつ癒してこれた。
そのことを、ようやく「よく頑張ってきたね」と自分に言えるようになりました。
これからも、愛着や対人関係について学び続けたい。
他人を理解するためというより、自分を大切にするために。
同じように悩む人へ
私は専門家ではないし、誰かにアドバイスできる立場ではありません。
でも、もし今「誰にも理解されない」と感じている人がいるなら、こう伝えたいです。
あなたは、あなたのままでいい。
あなたは素晴らしいものを持っていて、誰もあなたを否定しない場所がきっとある。
だから、どうか諦めないで。