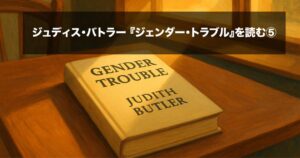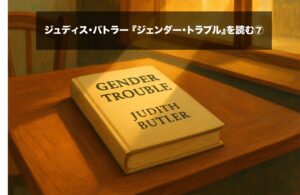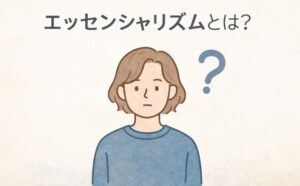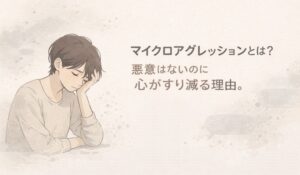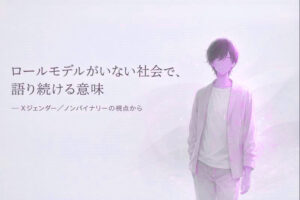3児の親であり、
Xジェンダー(ノンバイナリー)として「自分らしさ」を探求しながら発信しているユウです。
アライ(ally)とは、英語で「仲間」「同盟者」という意味の言葉です。
性的マイノリティ(LGBTQ+など)の文脈では「当事者ではないけれど、その人たちを支える存在」を指します。
アライがいる職場では、LGBTQ+の当事者が「心理的安全性(自分の意見や感情を気兼ねなく表現できる環境)」を感じられることが、アンケート調査で確認されています[1]。
また、学校や若者向け支援の研究では、アライや支援のある制度があることで、抑うつやストレスが少なく、幸福感(well-being)が高まることも示されています[2]。
この記事では、
・アライの意味と成り立ち
・アライの行動例や役割
・ノンバイナリーが抱える「見えにくさ」とアライとの関わり
・アライとしての葛藤や重さ
を、できるだけやさしく解説していきます。
参考資料
[1]認定NPO法人 虹色ダイバーシティ「niji VOICE 2020」
[2]The Trevor Project「Protective Factors for the Mental Health of LGBTQ+ Youth」
アライ(Ally)とは?定義と背景
アライの語源と意味
「アライ(Ally)」は英語の ally に由来し、直訳すると「仲間」「同盟者」「味方」という意味です。
もともとは国際関係や外交の場面で「同盟国」や「協力者」を指す言葉として使われてきました[3]。
その後、1980年代以降、大学や市民活動の場を中心に、LGBTQ+ の文脈で「性的マイノリティやジェンダーマイノリティを支える人」という意味で広く使われるようになりました[4]。
つまりアライとは、「自分は当事者ではないけれど、その立場に寄り添い、理解や支援を示す人」のことを指します。
誰がアライになれるのか
アライになるために特別な資格や条件は必要ありません。
たとえば、次のような人もアライになれます。
- 友人や家族として身近に支える人
- 職場や学校で理解や配慮を示す人
- 企業や自治体として制度や環境を整える立場の人
立場や役割に関わらず、「支えたい」という気持ちを持つ人なら誰でもアライになれます。
ただし「名乗るだけ」ではなく、日常の言葉づかいや行動にその姿勢を表していくことが大切です。
参考資料
[3] Merriam-Webster Dictionary “Ally” 定義
[4] Murdoch University “What is allyship? A brief history, present and future”
アライが取れる具体的な行動例
日常でできるアライの行動
アライは、日常生活の中でも小さな行動を積み重ねることで当事者を支えることができます。
例えば
・差別的な言葉やからかいを使わない
・いじめや偏見を見過ごさず注意する
・SNSで差別発言を見かけたら静かに指摘したり、正しい情報をシェアする
こうした一つひとつの行動は、当事者にとって「ここに味方がいる」と感じられる安心につながります。
学校や職場でのアライの実践
アライは個人だけでなく、学校や職場の中でも大切な役割を果たせます。
・学校で多様性をテーマにした授業や講演に参加する
・会社でのダイバーシティ研修を受け、職場環境を見直す
・履歴書やアンケートの性別欄を「男性・女性」だけでなく「その他・無回答」を選べるようにする
こうした制度や仕組みの改善は、当事者が「自分もここにいていい」と思える社会づくりに直結します。
参考資料
[5]滋賀県G-NET「ALLY(アライ)ってなに?」
[6]ReachOut Australia “How to be a good LGBTQIA+ ally”
アライの存在が必要な理由
LGBTQ+の若者を対象にした調査では、アライや支援的な大人の存在が「命や心の健康を守る要因」になることが明らかになっています。
The Trevor Project がまとめた研究レビューによれば、アライや支援的な教師・親がいる若者は、
・自殺を考える割合が大幅に低い
・抑うつ症状が少ない
・幸福感が高まる
といった結果が示されています[7]。
つまり、アライは単に「やさしい味方」というだけでなく、当事者の命や安心に直結する存在なのです。
参考資料
[7]The Trevor Project “Fostering the Mental Health of LGBTQ+ Youth”
アライがノンバイナリーにできること
ノンバイナリーの人は、社会の中で「自分の存在が認められていない」と感じやすい状況にあります。
これを「ノンバイナリー・インビジビリティ(見えにくさ)」と呼びます。
たとえば、書類の性別欄が「男性・女性」の二択しかないと、自分の居場所がないと感じてしまうことがあります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
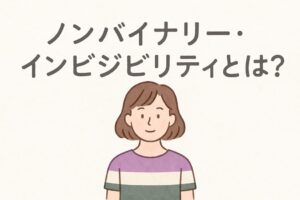
こうした「見えにくさ」を解消するために、アライは具体的にどんな行動ができるでしょうか。
・職場や学校で、性別にとらわれない制度や環境づくりを働きかける。
実際に日本の研究では、アライの存在が社会運動や制度改善の中で重要な役割を果たしてきたことが示されています[8]。
・アンケートや書類で「その他・無回答」といった選択肢を設けるよう提案する。
日本でも公立高校の入試願書から性別欄を撤廃する動きがあり[9]、社会全体で見直しが進んでいます。
・ノンバイナリーの可視化を進めるイベントや活動を応援する。
東京都の調査でも「トランスジェンダーに配慮した書類設計の必要性」が指摘されており[10]、アライが制度改善を後押しすることは現実的に意味があります。
こうした行動は、ノンバイナリー当事者にとって「自分は一人じゃない」と思える大きな支えになります。
参考資料
[8]J-STAGE論文「社会運動からAlly/アライを再考する」
[9]OUT JAPAN「高校入試で性別欄廃止の動き」
[10]東京都総務局調査「トランスジェンダーに配慮した書類設計」
アライの行動が社会を変える ー世界の事例ー
海外における制度的な変化とアライの後押し
海外では、ノンバイナリーやインターセックスの人たち自身が声を上げてきただけでなく、その周りで支えるアライ(支援者や団体、法律家など)の存在も大きな力になってきました。制度の変更は当事者の勇気ある行動から始まることが多いですが、それを社会全体に広げ、政府や裁判所に届ける役割をアライが担ってきたのです。
たとえばアメリカでは、インターセックス当事者の Dana Zzyym(ダナ・ジーム)氏 が、長年にわたり「X」の性別マーカー(男性でも女性でもないことを示す記号)が入ったパスポートを求めて裁判を起こしました[11]。
カナダでも、性別を「男性・女性」の二択でしか集めない調査や書類のあり方に対して、「それでは多様な人々を排除してしまう」と人権団体や支援者が訴えました。その結果、2017年にはパスポートで「X」を選べる制度が導入されました[12]。
さらにオーストラリアでは、Alex MacFarlane(アレックス・マクファーレン)氏 が2003年に世界で初めて「X」マーカー付きパスポートを手にしました[13]。
こうしたアメリカ、カナダ、オーストラリアでの制度的な変化の背景には、当事者の粘り強い訴えだけでなく、その声を社会に届け、法制度の改善を後押ししたアライの存在がありました。
法律家、人権団体、研究者、そして身近な支援者たちが「一緒に変えていこう」という姿勢を示したことで、個人の経験が社会全体の制度に反映されるまでに広がったのです。
参考資料
[11] Intersex Equality “Our A.D. is First Recipient of a US X Passport!”
[12] Trans activist settles human rights case about gender collection(2017)
[13] Wikipedia “Alex MacFarlane” 初の「X」性別マーカー付きパスポート取得例
アライとして名乗ることのプレッシャーと葛藤
名乗ることの意味とプレッシャー
「私はアライです」と名乗るのは、一見するとシンプルに思えるかもしれません。
けれど、その言葉には「正しい知識を持って行動できるのか」「本当に支えになれているのか」といったプレッシャーが伴います。実際に、アライと名乗った人の中には「自分の言葉や行動に責任を感じて、緊張してしまう」という声も少なくありません。
さらに、当事者から「ただ良い人に見られたいだけでは?」と受け止められてしまうリスクもあります。こうした“形だけのアライ活動”は「パフォーマティブ・アライシップ」と呼ばれ、海外でも議論されています。
たとえば Kutlaca & Radke(2023)は、見た目だけの支援は社会構造を変えることにはつながらず、むしろ当事者にとって負担になる場合があると指摘しています[16]。
同様に Forbes の記事でも、組織が「アライです」と表明するだけで、実際の制度改善や行動が伴わないケースは批判の対象になっていると述べられています[17]。
葛藤や孤独感
アライとして活動する中で、葛藤や孤独を感じる人も少なくありません。
・間違った発言をして当事者を傷つけてしまうのではないかという不安
・「もっと支えたいのに、どこまで踏み込んでいいかわからない」という迷い
・支える側であるはずなのに、相談できる相手が見つからず孤独を感じる経験
掲示板やアライのコミュニティでも、「精神的に重くなって疲れてしまった」という声が共有されています。
つまり、アライ自身も安心して話せる居場所や、支え合えるつながりを必要としているのです。
アライとしての苦悩について赤裸々に綴ったエッセイ、アミア・ミラーさん著の「ノンバイナリー協奏曲」という本について、こちらの記事でレビューを書いています。

アライが身近にいる当事者の方に読んで欲しい一冊です。
大切なのは「完璧さ」ではなく学び続ける姿勢
米国の人権団体 Human Rights Campaign も「アライに完璧さは求められない。大切なのは学び続ける姿勢と、日常の中で支援を示すこと」と指摘しています[18]。
また、The Trevor Project の調査でも、支援的な姿勢を持つ大人や仲間の存在が、LGBTQ+の若者のメンタルヘルスに大きな安心感を与えると示されています[19]。
このように、専門家や支援団体も「学び続ける姿勢こそがアライにとって重要」と強調しています。対話やフィードバックを重ねる中で、アライとしてのあり方は少しずつ育っていくと考えられます。
参考資料
[16]Kutlaca, M. & Radke, H. R. M. “Towards an understanding of performative allyship: Definition, antecedents and consequences”
[17]Forbes “Performative Allyship: What It Is and Why It Hurts”
[18]Being an LGBTQ+ Ally
[19] Fostering the Mental Health of LGBTQ Youth
体験談:アライをめぐって私が感じたこと
私は『ノンバイナリー協奏曲』という本を読んだとき、アライとして支えることの大変さを改めて考えさせられました。
読んでいて強く感じたのは、アライはただ「味方でいる」と言うだけではなく、その裏に孤独や葛藤を抱えていることもあるということです。
・誰にも相談できず、気持ちをため込んでしまう孤独感
・理解できないことを理解しなければいけないような重さ
・当事者にどこまで質問してよいのか迷うプレッシャー
私自身も、当事者として周りの人から「どう接してほしいか分からない」と言われた経験があります。
正直、戸惑うこともありました。
けれど「わからないから聞いてみたい」と思ってくれるその姿勢に、私はむしろ救われる部分もありました。
今の社会では、当事者に質問すること自体がタブー視される空気があるのも事実です。
だからこそ、私は「アライである」と名乗ってくれる人と当事者のあいだに、もっと安心して会話できる場が必要だと感じています。
そして、アライ同士での悩みや葛藤を安心して打ち明けられる場も同じように必要だと考えます。
もし、あなたがアライになりたいと思っているなら
もし、あなたが「アライになりたい」と思ってくれているのなら──その気持ちは、もうすでに誰かを救っています。
アライに完璧さなんていらないんです。
間違えてもいい、知らないことがあってもいい。
大切なのは「一緒に学びたい」「寄り添いたい」という心です。
学校で、たったひとこと「大丈夫だよ」と言ってくれる先生や友達がいたら、その子は安心して呼吸ができる。
職場で「ここにいていい」と示してくれる上司や同僚がいたら、その人は自分らしく働き続けられる。
メディアや文化の中で声を広げてくれる人がいれば、「私もここにいる」と言える人が増えていく。
あなたが「支えたい」と思うこと。
それだけで孤独を感じている誰かに光が届きます。
どうか恐れずに、迷わずに、その気持ちを大切にしてほしい。
アライでいてくれる人がいる──その事実だけで、どれほど多くの人が「ひとりじゃない」と思えることか。
私は心から、そういうあなたの存在を待ち望んでいます。
関連記事



FAQ
Q1. アライ(ally)とは誰のことですか?
A. 当事者ではないけれど、性的マイノリティを支えたいと考えて行動する人のことです。英語 ally の直訳は「仲間」「同盟者」です。
Q2. アライはどうやって名乗ればいいですか?
A. 特別な資格は不要ですが、日常の行動でその姿勢を示すことが大切です。「私はアライです」と言葉で伝えることも一歩になります。
Q3. アライとして失敗したらどうすればいいですか?
A. 間違えてしまったら、まずは素直に謝り、学び直せば大丈夫です。大切なのは「もう一度寄り添いたい」という姿勢です。
Q4. 企業や学校でできるアライの取り組みは?
A. すでに行われていることを例に挙げると、性別欄を見直す、研修や講演を実施する、相談窓口を設置するなどがあります。
Q5. ノンバイナリー・インビジビリティとアライはどう関係していますか?
A. ノンバイナリーは社会の中で見えにくい存在です。その存在を可視化し、理解を広げるためにアライの存在が欠かせません。
まとめ
・アライ(ally)とは「性的マイノリティを支える仲間」を意味する
・具体的な行動や言葉づかいが、当事者にとっての安心につながる
・ノンバイナリー・インビジビリティという「見えにくさ」を共に背負い、可視化を後押しする存在でもある
私自身も当事者であり、同時に自分にはないSOGIで悩む人のアライでありたいと思います。
もしあなたがアライになりたいと思っているなら、その気持ちが誰かを助ける一歩になります。
あなたは、あなたのままでいい。