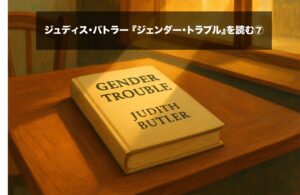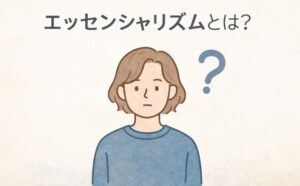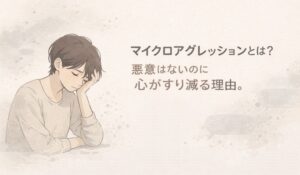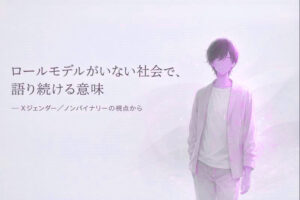セクシャリティとは、性別・性自認・性的指向・性表現など、
人間の性に関するあらゆる感覚や経験を指す包括的な概念です。
本記事では、セクシャリティの定義・種類・ジェンダーとの違いを
わかりやすく解説し、体験談も交えて深く考えていきます。
3児の親でありXジェンダー(ノンバイナリー)。
30歳から「自分らしい生き方」を探求中のユウです。
自分がセクシャルマイノリティであることを知るきっかけの一つに「セクシャリティ診断」というものがありました。
自分がどんなセクシャリティに当てはまるのかを無料で診断できるものです。
でも、診断を受けてみて、「そもそも、セクシャリティって何?」という疑問を抱きました。
自分では「性のあり方」全般に関することの総称として「セクシャリティ」という言葉を使っていたのですが、
この言葉にどんな要素が含まれるのかは、実のところよくわかっていませんでした。
そこで今回は、セクシャリティの話をするにあたって知っておくべき言葉について、それぞれの定義をまとめてみました。
セクシャリティとは

セクシャリティ(sexuality)とは、人間の性のあり方全般を指す包括的な概念です。
これは生物学的な性別だけでなく、性自認、性的指向、性表現、
さらには快楽や親密さなど、個人の性に関する多様な側面が含まれています。
世界保健機関(WHO)はセクシャリティを以下のように定義しています。
セクシャリティは、生涯を通じて人間であることの中心的側面であり、性、ジェンダー・アイデンティティと役割、性的指向、エロティシズム、快楽、親密さ、生殖を含む。セクシャリティは、思考、空想、欲望、信念、態度、価値観、行動、実践、役割、人間関係を通じて経験され、表現される。セクシャリティはこれらすべての次元を含みうるが、必ずしもすべてが経験・表現されるわけではない。セクシュアリティは、生物学的、心理学的、社会的、経済的、政治的、文化的、法律的、歴史的、宗教的、精神的要因の相互作用によって影響される。
WHOのページはこちら
米国心理学会(APA)は、セクシャリティを性行動のあらゆる側面(性自認、性的指向、態度、活動など)を含むものと定義しています。
また、性的指向や性自認は人間の自然な一部であり、同性愛や両性愛などの性的指向は正常で肯定的な人間のセクシュアリティの変異であると明言しています。
参考:https://www.apa.org/topics/sex-sexuality?utm_source=chatgpt.com
https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation?utm_source=chatgpt.com
セクシャリティを構成する4つの要素
セクシャリティは主に、以下の4つの要素から構成されます。
1. 生物学的な性(Sex)
生まれ持った身体的特徴(外性器、内性器、染色体など)に基づいて割り当てられる性別。
出生時に「男性」または「女性」として登録されますが、インターセックスのように一概に分類できないケースも存在します。
2. 性自認(Gender Identity)
自分自身が認識する性。「男性」「女性」のほか、「ノンバイナリー」や「クエスチョニング」など、多様な性自認が存在します。
3. 性的指向(Sexual Orientation)
恋愛感情や性的魅力を抱く対象の性別。異性愛、同性愛、両性愛、アセクシュアル(無性愛)など、多様な指向があります。
4. 性表現(Gender Expression)
服装、言動、態度など、外部に表現される性のあり方。
「男性らしさ」「女性らしさ」といった社会的期待に基づくものも含まれますが、個人の選択によって多様な表現が存在します。
セクシャリティの種類と用語解説
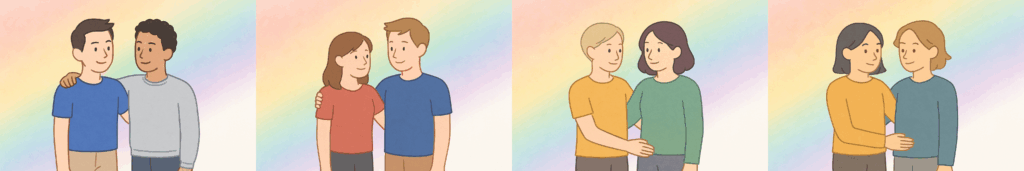
電通「LGBTQ+調査2023」(2023年)
電通の最新調査によると、全国20〜59歳の約57,500人を対象に実施された調査で、日本におけるLGBTQ+層の割合は9.7%と報告されています。
セクシャリティにはさまざまな種類があります。以下に代表的なものを紹介します。
レズビアン(Lesbian):性自認が女性で、女性に恋愛感情を抱く人。
ゲイ(Gay):性自認が男性で、男性に恋愛感情を抱く人。
バイセクシュアル(Bisexual):男性・女性の両方に恋愛感情を抱く人。
トランスジェンダー(Transgender):生物学的な性と性自認が一致しない人。
アセクシュアル(Asexual):他者に性的魅力を感じない人。
パンセクシュアル(Pansexual):性別に関係なく恋愛感情を抱く人。
ノンバイナリー(Non-binary):「男性」「女性」のいずれにも当てはまらない性自認を持つ人。
英語の語源から見るセクシャリティ用語
セクシャリティに関する用語の多くは、英語の接頭辞や語源に由来しています。以下にいくつかの例を紹介します。
参考:Sports for Social
トランスジェンダー(Transgender):「trans-」はラテン語で「向こう側の」を意味し、生物学的な性と性自認が一致していない人を指します。
シスジェンダー(Cisgender):「cis-」はラテン語で「こちら側の」を意味し、生物学的な性と性自認が一致している人を指します。
バイセクシュアル(Bisexual):
「bi-」は「二つ」を意味します。男女どちらにも惹かれる人を指しますが、近年は性別の二元論にとらわれず「複数の性に惹かれる」意味でも使われています。
パンセクシュアル(Pansexual):
「pan-」は「すべて」を意味し、性別に関係なく惹かれる人を指します。恋愛や性的魅力を抱く際に、相手の性別が要素にならない人も多いです。
アセクシュアル(Asexual):
「a-」は「無い」「否定」を意味します。他者に性的な欲求や魅力を抱かない人のこと。恋愛感情を持つかどうかはまた別の概念です(ロマンティック指向と呼ばれます)。
クィア(Queer):
もともとは「風変わりな」という意味の言葉でしたが、今では「どの枠にもおさまらない多様な性」を肯定的に表現する言葉として使われています。
もっとたくさん用語が知りたい!という方のために、セクシュアリティ用語をまとめています。

私がセクシャリティと出会った瞬間
高校生の頃の私は、「誰かを好きになる」という感覚そのものにピンときていませんでした。
誰かの恋バナを聞くのは大好きだったけれど、それが自分に当てはまっている様子が全く想像できませんでした。
周りの人たちは好きな人がいるのが「普通」で、いない私は「遅れてる」、「経験がないだけ」。
自分のことを聞かれると、笑ってごまかしたり、適当に話を合わせたりしていたけど、ずっと「私は他の子と何かが違う」と感じていました。
そして大人になり、パートナーと出会い、子どもを授かったあと、「私はもう女性でいたいと思わない」とはっきり思いました。
私は「女性」として育てられたけれど、心のどこかでずっと、そこに違和感があった。
いまの私は、自分のことを「ノンバイナリー」や「Xジェンダー」、「Aceスペクトラム」として表現しています。
よくある誤解とその背景

「セクシャリティは生まれつき?」
生まれつきの場合もありますが、人生経験や環境により変化する人もいます。
私も30歳になるまでは「女性」として生きてきましたが、現在はXジェンダー(ノンバイナリー)として生きています。
セクシャリティは“変わってもいい”ものです。
「LGBTQ+は“少数派”だから特別?」
人口に占める割合の大小に関わらず、誰もが自分の感覚を尊重される権利があります。
それは、LGBTQに限りません。
「男らしさ・女らしさ」は必要?
社会的に作られた「らしさ」に縛られずに、自分の心にフィットする表現を選ぶ自由があります。
それが性表現です。
性的指向と性自認は誰でも持っているものです。この二つの言葉を合わせたSOGIについて、こちらの記事でまとめています。

セクシャリティとジェンダー、性別の違い
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 性別(Sex) | 生物学的・身体的な性のこと。男性・女性・インターセックスなど。 |
| ジェンダー(Gender) | 社会的・文化的に形成された性役割。男性らしさ、女性らしさなど。 |
| 性自認(Gender Identity) | 自分自身が思う性。男性、女性、ノンバイナリーなど。 |
| セクシャリティ(Sexuality) | 性に関するすべての個人の感覚。恋愛感情・性表現・性の快楽なども含む。 |
ジェンダー(Gender)は「セクシャリティの構成要素ではない」
ここで重要なのは、「ジェンダー(Gender)」だけが、セクシャリティの“内部要素”ではない、という点です。
セクシャリティは、性自認・性的指向・性表現・快楽・親密さなど、個人の性に関する内的・外的な感覚を含みます。
一方、ジェンダーは社会や文化がつくる「枠組み」であり、セクシャリティを取り巻く“外側”の環境のようなもの。
セクシャリティは「自分の心と身体の中にあるもの」で、ジェンダーは社会が与える「ふるまい方」の枠組みなのです。
世界と日本のセクシャリティを取り巻く環境
世界の取り組み:認知と制度が進む国々
近年、多くの国でセクシャルマイノリティの権利が保障されるようになり、ジェンダーやセクシャリティに関する制度も整ってきています。
カナダ、ドイツ、ニュージーランドなどでは、パスポートに「X(その他)」を性別として選べるようになっており、法的にノンバイナリーを認める動きが進んでいます。
オランダやスウェーデンでは、性別変更において身体的手術の要件が撤廃され、個人の自己決定が尊重されています。
同性婚を認める国も増加しており、2024年時点で30以上の国で合法化されています。
こうした国々では、セクシャリティは「人権のひとつ」として認識されつつあります。
日本の現状:法制度と社会のギャップ
日本でも、LGBTQ+に関する理解は少しずつ進んできていますが、制度面ではまだ課題が多く残っています。
性別の法的変更には、性別適合手術の実施が事実上求められている(戸籍法 第107条の3)
性別の法的変更に性別適合手術は完全には求められなくなっていますが、ケースによっては依然として一部の手術が必要とされる可能性があります。
同性婚は法律上認められておらず、自治体単位での「パートナーシップ制度」が主流。法的効力は限定的です。
学校や職場での性的マイノリティへの対応も未整備な部分が多く、カミングアウトや配慮を求めることに不安を感じる当事者も少なくありません。
セクシャリティを考えることは「自分を大切にすること」
「こんな自分、変じゃないかな…」
「周りに合わせなきゃ、受け入れてもらえないかも」
そんな不安を抱えていた頃の私に、今ならこう言いたい。
「あなたは変じゃない、そのままでいいんだよ。」
セクシャリティは、社会の決まりや他人の期待に合わせるためのものではなく、
あなた自身の“心の輪郭”です。
「私は私」と言えるようになるまでには、時間がかかるかもしれません。
でも、そのプロセスを否定せず、大切にしてほしいと思います。
まとめ|セクシャリティは、誰にとっても“自分を知る鍵”
セクシャリティとは、性に関するあらゆる個人の感覚を含む広い概念。
生物学的性、性自認、性的指向、性表現など多様な要素が含まれる。
LGBTQ+などの用語は、自分の感覚を表現する“選択肢”のひとつ。
自分らしくあることを選び取るには、言葉や知識が「支え」になる。
あなたは、あなたのままでいい

自分のセクシャリティに悩んでいるときは、
孤独の中で「世界にたった一人きり」になったように感じることもあるかもしれません。
でも、あなたは一人じゃありません。
この記事をここまで読んでくれたあなたも、私と同じように、「ほんとうの自分」で生きることを大切にしたいと思っているはずです。
どうか、自分を否定しないで。
あなたの感覚は、あなただけの宝物なんですから。