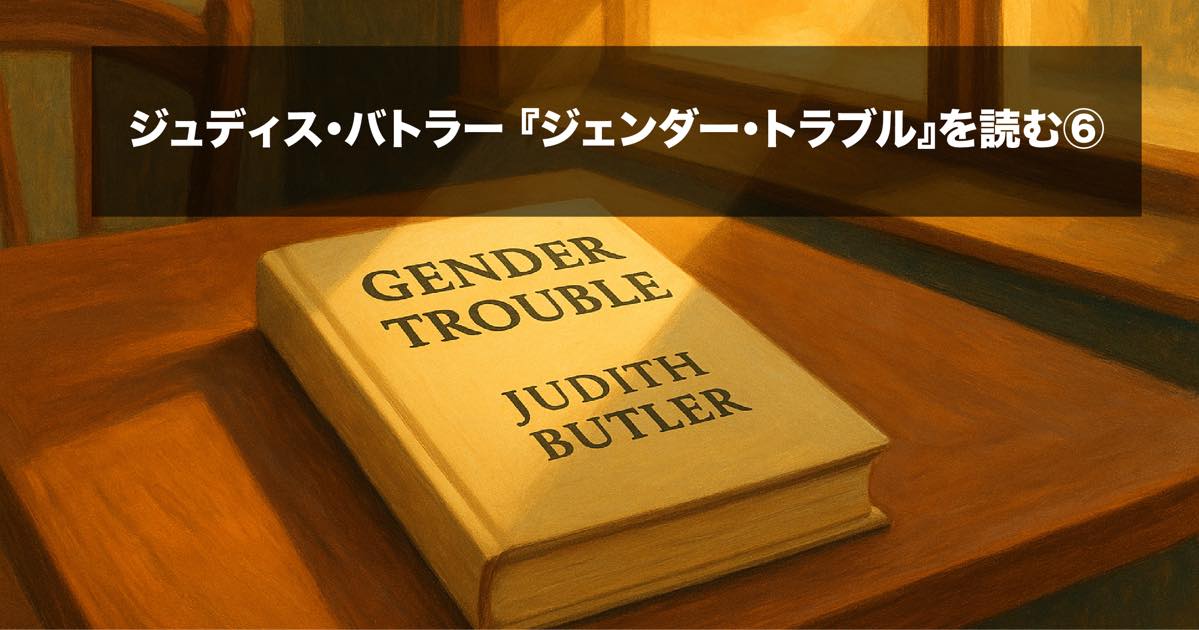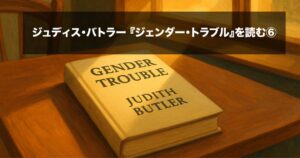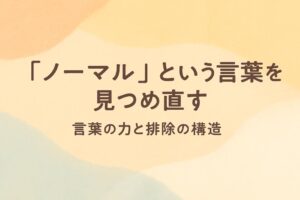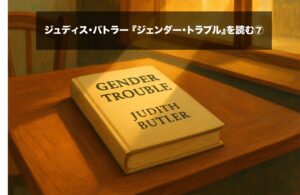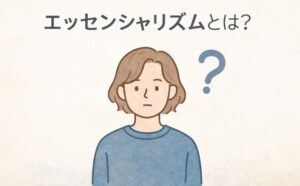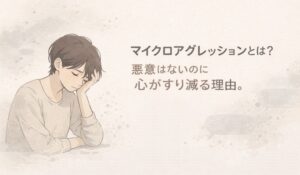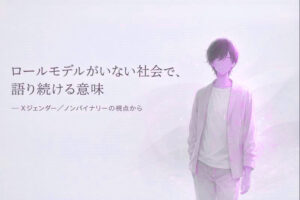世界のフェミニズムやクィア理論を語るときに、必ず名前が出る名著——ジュディス・バトラーの 『ジェンダー・トラブル(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity)』。
「ジェンダーは生まれつきではなく“演じられるもの”だ」という衝撃のアイデアを提示し、フェミニズム理論の歴史を大きく塗り替えた一冊です。いまや世界中の大学で必読文献とされ、出版から30年以上たった今でも引用され続けています。
そんなとんでもなくすごい本が、オープンアクセスで誰でも無料で読めるのです。
しかし、実際にページを開いてみると、「英語」「哲学用語だらけ」「とにかく難しい」という三重苦。
そこで私は決めました。ChatGPTに“中学生でもわかるように”かみくだいてもらいながら、この本を少しずつ読み進め、解説していこうと。
このシリーズでは、フェミニズムやクィア理論について知識0の筆者が、難解な議論を肩ひじ張らずに解説しつつ、私自身の「なるほど!」「ここわからん!」といったリアルな反応も残していきます。
名著を一緒に探検するような気分で、ゆるく楽しんでもらえたら嬉しいです。
前回までの内容はこちらです。
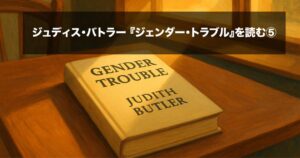
今日は第1章の「vi. Language, Power, and the Strategies of Displacement」のパートについてchatGPTに解説してもらいました。
ジェンダーは「振る舞っているうちに、そうなっていく」
「男らしさ」や「女らしさ」って、もともと体の中にあるものだと思っていませんか?
でもジュディス・バトラーはこう考えました。
「ジェンダーは生まれつきの“本体”ではなく、社会の中でくり返し演じることで作られていく。」
たとえば、学校でランドセルの色は「男の子は黒」「女の子は赤」と言われていた時代がありました。
親や先生に「そういうものだ」と教えられ、少しずつ“らしさ”が形になります。
最初から「男らしさ」や「女らしさ」が子どもたちの中にあるわけじゃない。
らしく振る舞っているうちに“そう見えるようになっていく” のです。
「行動が“自分”を作る」演じるという考え方
バトラーは、「行動が先で、“自分”という本体はあとからできる」と言います。
つまり、
「本体があるから行動する」ではなく、「行動するから本体があるように見える」
多くの人は、「男だからこう振る舞う」「女だからこう感じる」というように、
“性別という本体が先にあって、それにふさわしい行動をしている”と考えがちです。
でも、バトラーはその考えをひっくり返します。
「“本体”があるから行動する」のではなく、「行動するから“本体”があるように見える」のだ、と。
ここでいう“本体”とは、「変わらない中心のようなもの」のような意味です。
もともとは古代ギリシャの哲学者アリストテレスの考え方で、
「人や物には、見た目や性質が変わっても変わらない“本質”がある」とされていました。
たとえば、“火”はいつでも熱い、“水”はいつでも流れる、というように。
そしてその考えを「人間」に当てはめたときに、「男」と「女」という
性別そのものが変わらない“本体”であるかのように見なされてきたのです。
しかしバトラーは、「実はその“本体”らしさは、
社会の中で何度も同じように演じられることで作られた“見かけ”なのでは?」と問いかけます。
たとえば、『ベルサイユのばら』のオスカル。
体は女性ですが、幼いころから男として育てられました。
その結果、「男として生きること」が自然になっていった。
『もののけ姫』のサンも同じです。
人間として生まれたのに、自分を“山犬の一族”として生きている。
育てられ方や環境によって、「自分とは何者か」が変わる ということ。
バトラーが言う「ジェンダーの演技」は、まさにこのようなプロセスのことなんです。
言葉が押す“見えないスタンプ”——社会が性別を作る仕組み
社会は、「女らしさ」「男らしさ」という言葉を使いながら、
私たちに“見えないスタンプ”を押しています。
たとえば、
- 「女の子なんだから、優しくしなきゃ」
- 「男の子なんだから、泣くな」
そんな言葉を何度も聞くうちに、
「そうしなきゃいけない自分」 が形づくられていく。
つまり、性別は“体の違い”よりも、“言葉の使われ方”によって強化されていくんです。
ウィッティグとイリガライ——言葉は変えられる? それとも最初から偏ってる?
ここで、2人の女性思想家の考え方を紹介します。
どちらも「言葉が性別をどう作っているか」を考えた人たちです。
① ウィッティグの考え方
- 「女/男」という区分は、社会が押した“印”にすぎない。
- 言葉は道具。使い方を変えれば、社会も変えられる。
- たとえば、“妻”や“母”という言葉の代わりに、“パートナー”という言葉を使うことで関係の形も変わる。
ウィッティグは、言葉の使い方を工夫することで
「異性愛中心の世界」を揺さぶることができると考えました。
② イリガライの考え方
- 社会の言葉そのものが、男性の視点で作られている。
- だから、女性は“書かれない”“見えない”存在になりがち。
- 抜け出すには、「女性の感覚」を生かした新しい言葉を作る必要がある。
ウィッティグは「言葉を使い直す」派、
イリガライは「言葉の土台から変える」派。
どちらも、“言葉が性別を作る力”を意識していました。
“父の法”って何?——ラカンの考え方も登場
ここで登場する「父の法」という言葉、ちょっとびっくりしますよね。
これは、心理学者ラカンの考え方です。
彼の言う“父の法”とは、
「社会の中で“やっていいこと・悪いこと”を教える見えないルール」
のこと。
たとえば、
- 「男の子は泣いちゃダメ」
- 「女の子は優しくしなさい」
- 「家族はこうあるべき」
こうした“常識”は、親や学校、社会の中で自然と学びます。
この“ルールの網の目”が、ラカンのいう「法」なのです。
そして、このルールの中で私たちは「男」「女」としてふるまうことを覚えていく。
つまり、社会の仕組みそのものが、性を形づくっている という考え方です。
バトラーの批判:その“法”の中でどう生きるか
バトラーは、ラカンの考えに対してこう問いかけます。
「社会のルールの中で性が作られるのはわかる。でも、“ルールの外”に出ることはできないの?」
完全に外には出られない。
けれど、同じルールをくり返す中で少し“ズラす”ことはできる。たとえば——
- 学校で「男子=学ラン・女子=スカート」だった制服を、どちらでも選べる形に変える。
- 家の中で「お母さんが全部家事をする」ではなく、家族で分担を話し合う。
- 会社で「男の上司が指示を出す」のが当然だったのを、誰でも意見を言える会議にする。
こうした小さな変化は、
「女だからこうする」「男だからこう振る舞う」という見えないルールをゆるめていきます。
つまり、「ズラす」とは
“性別で決まっていた当たり前”を、
“誰でも選べる当たり前”に少しずつ変えていくこと。
バトラーは、「社会をひっくり返すような大改革じゃなくてもいい」と言います。
今ある場所で、ちょっと違う選び方・話し方・振る舞い方をくり返すこと。
その積み重ねが、より自由な生き方を作っていくのです。
“外へ逃げる”より、“内でズラす”——フーコーの考え方とつながる
バトラーの考えには、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの影響が強くあります。
フーコーはこう言いました。
「権力は人を縛るだけでなく、新しい生き方を生み出す力も持っている。」
私たちは「権力」と聞くと、
「支配する」「押さえつける」「自由を奪う」といったイメージを持ちますよね。
でもフーコーは、それだけではないと考えました。
たとえば——
昔の学校では、制服・髪型・男女のルールがとても厳しく決められていました。
「男子は黒い学ラン」「女子はスカート」といった決まりもその一つです。
でも最近では、
- 「スラックスかスカートを選べる制服」
- 「髪型は自由」
- 「性別欄は“書かなくてもいい”」
といった形に、少しずつ変わってきています。
これらの変化は、「古いルールを全部壊す」という“外へ逃げる”やり方ではありません。
ルールの中で、違うやり方を試してみることから始まっています。
つまり、
「権力=社会のルールや仕組み」そのものを全部なくすことはできない。
でも、その“中身の使い方”を変えることで、新しい生き方は生まれる。
バトラーは、このフーコーの考えを受け継いでいます。
「男/女」という枠組みを完全に消すのではなく、
その中での演じ方・表現の仕方を変えることで、枠組みそのものをゆるめていく。
たとえば、
- 「女性だけどスーツを着たい」
- 「男性だけど保育士として働きたい」
- 「どちらにも当てはまらないけれど、自分らしく名乗りたい」
こうした“ズラし”は、権力の外ではなく、内側から生まれる自由の形です。です。
「コピーのコピー」パロディが社会を変える?
ここでバトラーはおもしろい例を出します。
「男らしさ」「女らしさ」は“原型”のように見えるけど、
実はどれも“誰かのマネ(コピー)”だというのです。
ドラァグクイーンのパフォーマンスはその典型です。
彼女たちは「女性らしさ」を誇張して演じることで、
“女らしさ”が「自然なもの」ではなく「作られたもの」だと気づかせてくれます。
つまり、ズラし=パロディ(演じ方を変えること) が、
社会のルールそのものを問い直す力になるのです。
考え続けるという“演じ方”——バトラーを読んで感じたこと
今回の記事を書くにあたって、私は何十もの質問をChatGPTに投げかけました。
「“外へ逃げる”ってどういうこと?」「“ズラす”って何?」「本体ってなに?」
読めば読むほど疑問が増えていって、まるで霧の中を歩いているような感覚でした。
でも、その“わからなさ”の中で少しずつ見えてきたのは、
「ジェンダーは生まれつきの本体ではなく、社会の中で演じられているもの」
ということ。
「男らしさ」「女らしさ」は、私たちが自然に身につけた性質ではなく、
社会という舞台の上で繰り返し演じてきた“役”のようなものかもしれません。
たとえば——
「男の子は青」「女の子はピンク」
「母親だから家事」「父親だから外で働く」
こうしたルールに従うことで、社会の“見えない脚本”を演じてきたのです。
でも、演じ方を変えることはできると思うのです。
日常の中でできる“ズラし”の練習
難しい哲学の話も、結局は日常の中に落とし込めます。
たとえば、こんな小さな選択から始めてみることができるかもしれません。
- 「彼」「彼女」ではなく「パートナー」と言ってみる
- プロフィール欄の性別を“未設定”にしてみる
- 家事や育児の役割を「女性らしさ/男性らしさ」で決めない
- 子どもに「男の子だから」「女の子だから」と言わない
こうした小さな“ズラし”の積み重ねが、
社会の“見えない法”——つまり、
「こうでなければならない」という固定観念を少しずつゆるめていくのではないでしょうか。
今回はテーマごとにchatGPTを質問攻めにしました
毎回解説を作るのは難しいのですが、今回はそれに加えて「長い」という大変さがありました。
そこで、chatGPTにある程度まとまったテーマに分けてもらい、テーマの概要について質問をしていきながら理解を深めるという方法をとりました。
個人的には今までで一番わかりやすい記事になったような気がします。
どういう質問をすればわかりやすい記事が作れるか、これからも試行錯誤してみます。
まとめ:「ルールの中でズラす」ことから始めよう
バトラーの考えを一言でまとめると、こうです。
ジェンダーは“本体”ではなく、“演じ方の積み重ね”で形づくられる。
外の世界に“正解の性”があるわけではない。
でも、今あるルールの中で演じ方をズラすことで、新しい形が生まれる。
それは「逃げる」ことではなく、「中から世界をゆるめる」こと。
誰かの“当たり前”を、少し変えていく小さな革命です。