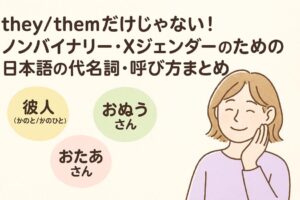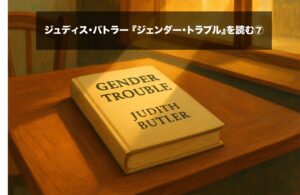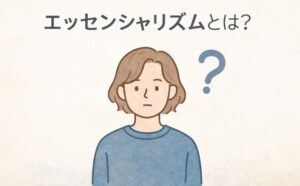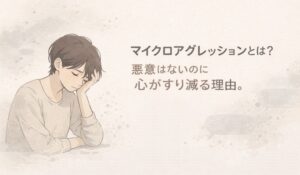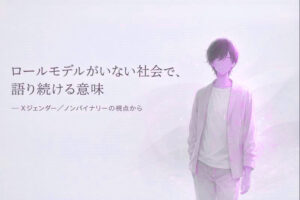3児の親であり、
ノンバイナリーとして「自分らしい生き方」を探求中のユウです。
最近、「SOGI(ソジ)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
でも、「LGBTQは聞いたことあるけど、SOGIって何?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
SOGIとは、「性的指向(Sexual Orientation)」と「性自認(Gender Identity)」を合わせた言葉で、
すべての人に関係がある「性のあり方」を指す概念です。
たとえば、
「自分は女性で、男性が好き」という人にも
「自分は男性で、男性が好き」という人にもSOGIがあるし、
「自分の性別がはっきりしていない」と感じる人にも、もちろんSOGIがあります。
LGBTQという言葉は、性的マイノリティのラベルとして知られていますが、
SOGIは“誰もが持っているもの”として、もっと広く・深く、私たち自身の在り方を表す言葉です。
この記事では、「SOGIとは何か?」という基本から、LGBTQとの違い、
そして「SOGIという視点を持つことがなぜ大切なのか」について、に解説していきます。
SOGI(ソジ)とは?誰にでもある“性のあり方”
SOGIの意味と読み方:性的指向と性自認の略語
SOGI(ソジ)とは、「Sexual Orientation and Gender Identity(性的指向と性自認)」の頭文字を取った言葉です。日本語では「ソジ」と読みます。
性的指向(Sexual Orientation)
恋愛感情や性的魅力を誰に抱くか、あるいは誰にも抱かないかという傾向。
「誰を好きになるか」という感覚。
性自認(Gender Identity)
自分がどの性別であると感じているかという、本人の認識。
身体的性別と一致する場合もあれば、一致しない場合もあります。
※性的指向と性自認については、あとで詳しく解説しています。
この言葉はもともと、国連や国際人権機関などで使われてきたもので、差別をなくすために「すべての人の性の在り方」を尊重する視点として広まりました。
SOGIを理解する上で大事なポイントは、SOGIは“特別な人だけ”の言葉ではないということ。
性的指向(Sexual Orientation)がどの性別に向く人も、あるいは向かない人も、
性自認(Gender Identity) が男性でも、女性でも、男女に当てはまらなくても。
すべての人がそれぞれのSOGIを持っているのです。
ここでちょっと、この記事を読んでくださっているあなたのSOGIは何か、
改めて考えてみてください。
あなたも必ず、説明できるSOGIを持っています。
自分がどんなSOGIを持っているかは、セクシュアリティ診断で調べることもできます。

性的指向とは?恋愛・性愛の対象をどう感じるか
「性的指向(Sexual Orientation)」とは、どんな相手に恋愛感情や性的な魅力を感じるかという個人の傾向を表す言葉です。
たとえば、
- 異性を好きになる → 異性愛(ヘテロセクシュアル)
- 同性を好きになる → 同性愛(ゲイ/レズビアン)
- 男女どちらにも惹かれる → 両性愛(バイセクシュアル)
- 誰にも恋愛感情を持たない → アロマンティック
- 誰にも性的欲求を感じない → アセクシュアル
このように、恋愛感情や性的感情の「有無」「対象」には、多様な形があります。
このような、性のあり方に関する用語については、こちらにまとめています。
あなたはどれに当てはまるでしょうか。
性自認とは?自分の性別をどう認識しているか
「性自認(Gender Identity)」は、自分自身の性別をどう認識しているかを指します。
それは必ずしも、身体的な性別(いわゆる“生まれたときに割り当てられた性”)と一致するとは限りません。
- 自分を女性と感じる → 女性(ジェンダー・アイデンティティ:女性)
- 自分を男性と感じる → 男性
- 男性でも女性でもない/そのどちらにも当てはまらない → ノンバイナリー、Xジェンダー、アジェンダーなど
性自認は自分自身が性別をどう認識しているかという感覚で、他人が外から決められるものではありません。
わたし自身も、自分の性別にピンとこない感覚を持ち続けてきたひとりです。
「女性」でも「男性」でもない“どちらでもない自分”として、自分なりの心地よさを探しながら生きています。
性的指向や性自認などの性のあり方に関する用語は、こちらの記事にまとめています。
あなたを表す言葉もきっと見つかるはずです。

「LGBTQ」と「SOGI」の違いとは?
LGBTQは“特定の人”のラベル/SOGIは“すべての人”の感覚
「LGBTQ」という言葉は、多くの人にとって耳なじみがあると思います。
Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアル、Tはトランスジェンダー、Qはクエスチョニングやクィアを意味します。
これらは、いわゆる性的マイノリティを指すラベルとして広く使われてきました。
その一方で、「LGBTQの人=自分とは違う特別な人」という“線引き”が、無意識のうちに生まれてしまうことがあります。
それに対して、SOGIはすべての人に当てはまる概念です。
誰もが持っている「性的指向」と「性自認」に名前をつけたものであり、
「あなたにも私にもSOGIがある」という立場から出発します。
だからこそ、SOGIという視点を持つことで、
LGBTQの人々を「理解すべき対象」ではなく、
「同じように自分自身のSOGIを持つ仲間」として自然に受け止めやすくなるのです。
LGBTQの分類と略語の意味をおさらい
ここで一度、LGBTQという言葉が表す内容もおさらいしておきましょう。
L:レズビアン(同性の女性を恋愛対象とする女性)
G:ゲイ(同性の男性を恋愛対象とする男性)
B:バイセクシュアル(男女どちらも恋愛対象に含む)
T:トランスジェンダー(出生時に割り当てられた性別とは異なる性自認を持つ人)
Q:クィア/クエスチョニング(既存のラベルに当てはまらない、または探している途中の人)
これらの言葉は、特定の枠組みを持つ当事者たちが、自分自身を説明するために使ってきたラベルです。
一方で、SOGIはそれらを含んだうえで、「すべての人に共通する軸(指向と自認)」を示しています。
SOGIという言葉が国際的に広まった背景
SOGIの「性的指向」を国際人権の土台にした出来事
1992年/Toonen判決(トゥーネン事件)
1992年、オーストラリア・タスマニア州では、合意のある男性同士の関係を法律で罰する規則が残っていました。
これに対し、当事者のニコラス・トゥーネンさんは、国連人権委員会(UN Human Rights Committee)に訴えを起こします。
国連は、国際人権規約(ICCPR)の第2条・第26条にある「性(sex)」という言葉には、“誰を好きになるか”(性的指向:Sexual Orientation)も含まれると初めて認めました。
この判断により、愛する相手の性別に関わらず、それは守られるべき権利だという考え方が世界に広がりました。
この判決は、SOGIの「SO(性的指向)」を人権として国際法上で明確に位置づける重要な第一歩となりました。
参考リンク:国連人権委員会・判決全文(英語PDF)
SOGIの「性自認」も含めて国際原則にまとめた出来事
2006〜2007年/ヨギャカルタ原則
2006年11月、インドネシアのジョグジャカルタにあるガジャ・マダ大学で、人権の専門家たちが会議を開きました。
この会議では、「好きになる相手(性的指向)」だけでなく、「自分をどんな性だと感じているか(性自認:Gender Identity)」も守られるべき人権だと定義されました。
その内容は2007年に「ヨギャカルタ原則(Yogyakarta Principles)」として発表されました。
この原則は法律のような強制力は持ちませんが、国連人権理事会の議論や各国の政策で引用され、SOGIという考え方が国際的に広まるきっかけになりました。
参考リンク:ヨギャカルタ原則公式サイト(英語)
国際的なSOGIの動き
国連でのSOGI保護の強化
2016年、国連人権理事会は初めて、性的指向や性自認に基づく暴力や差別に対応する「独立専門家(Independent Expert on SOGI)制度」を設立しました。
これは、SOGIに関する人権侵害を監視・報告し、改善を促す役割を担う制度です。
国際司法裁判所(ICJ)発表資料はこちら
2025年にはこの制度の延長が決議され、世界157か国・地域から1,259団体が賛同署名を行い、29か国の賛成で採択されました。
ILGA Worldの報告はこちら
この動きは、SOGIの保護が国際的に継続して強化されていることを示しています。
SOGIハラとは?定義と日本での広がり
SOGIハラの意味
SOGIハラとは、性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)に関する嫌がらせや差別的な言動のことです。
たとえば
- 「男らしくない」「女らしくない」と決めつける発言
- 恋愛対象や性自認をからかう、否定する
- 無理に恋愛や結婚の話題を押しつける
こうした行為は、相手がLGBTQかどうかに関係なく、誰でも被害者にも加害者にもなり得ます。
この点が、性的マイノリティだけに焦点を当てた差別用語とは異なる特徴です。
日本でのSOGIハラという言葉の普及の流れ
2010年代前半:概念としての存在
LGBTQの差別自体は認識されていましたが、「SOGIハラ」という用語はまだ広くは使われていませんでした。
2015年〜:LGBTQの認知度アップ
渋谷区が同性パートナーシップ証明を導入(2015年4月)し、LGBTQの関心が高まって以降、SOGIという言葉も少しずつ行政や教育の文脈で使われ始めました。
2019年:厚生労働省が指針で明記
改正された「労働施策総合推進法」に基づく指針(いわゆるパワハラ防止指針)で、性的指向・性自認に関する侮辱的な言動(SOGIハラ)を具体例として挙げ、パワハラの一部として明記されました。
厚生労働省:職場におけるパワーハラスメント防止指針(PDF)
2020年代:SDGs・多様性推進との連動で定着
SDGs(目標5:ジェンダー平等)や企業・自治体でのD&I推進活動の中で、「SOGIハラ」という言葉が研修や方針などに登場する機会が増えています。
※D&I推進活動とは、企業や行政、教育機関などが、「多様な人が平等に機会を得て活躍できるようにするための取り組み」 を計画・実行する活動のことです。
SOGIハラの社会的背景と現在の位置づけ
もともとSOGIハラは、LGBTQなど性的マイノリティの人たちが受ける差別や嫌がらせを指す場面が多くありました。
しかし、SOGIが「すべての人に性的指向と性自認がある」という考え方として浸透してきたことで、
現在では「誰もが当事者になり得るハラスメント」として捉えられています。
こうした動きは、「特別な人を守る社会」から「すべての人を尊重する社会」へ転換する大きな変化を示しています。
なぜ今「SOGI」が注目されているのか
日本でも、近年は教育・職場・行政の現場で「SOGI」という言葉が使われ始めています。
その背景には、「LGBTQ」というラベルだけでは拾いきれないグレーゾーンの存在、
そして、“マイノリティ”と“マジョリティ”を切り分けない新たな視点へのニーズがあるからです。
たとえば、
- 自分の性自認には違和感がないけれど、他者の性別表現を尊重したい
- 恋愛や性に関心がないけれど、無理に当てはまるラベルが見つからない
- 子どもに「多様性って何?」を自然に伝えたい
そんな場面でも、SOGIという言葉を使えば、「特別な人の話」ではなく「自分ごと」として語ることができます。
わたし自身も、「ノンバイナリーです」と名乗るよりも、
「SOGIの視点から発信しています」と言った方が、相手との距離が近くなると感じています。
SOGIは誰にでもある:マジョリティにも“性の多様性”がある
「自分は関係ない」と思う人こそ知ってほしい理由
「自分はふつうの男女の恋愛をしてるし、性別にも違和感はないから、SOGIの話は関係ない」
そう感じる人もいるかもしれません。
でも実は、その“ふつう”だと感じている性のあり方も、あなた自身のSOGIなんです。
「異性愛者で、性自認は男性」
「恋人はいるけど、結婚には興味がない」
「自分を女性だと認識しているが、男性的な服装が好き」
それぞれの性のあり方には、他の誰とも同じでない個別の感覚があります。
だからこそ、SOGIは“全員が持っている”という視点が大切です。
マイノリティかどうかではなく、すべての人が「自分のSOGIに気づく」ことから、違いを尊重する感覚が育っていくのではないかと私は思っています。
SOGIの視点から社会を見直すと、差別はどう変わる?
差別や偏見は、「自分とは違う存在」への誤解や距離感から生まれやすいものです。
でも、「自分にもSOGIがある」と気づいたとき、その“違い”は「対岸のもの」ではなくなります。
たとえば、
- 性自認が一致しないことで戸惑う人
- 恋愛や性愛の感覚に名前をつけられず苦しむ人
- 「それって変じゃないの?」と否定される経験を持つ人
こうした人たちを、「理解しようとがんばる」のではなく、
「自分もSOGIがあるから、違って当然だよね」と自然に受け入れられるようになる。
それが、SOGIという視点がもつ力だと感じています。
私が「SOGI」という言葉に惹かれた理由
私がSOGIという言葉を知ったとき、最初に感じたのは「これだ」という安心感でした。
ノンバイナリーやXジェンダーといったラベルを名乗るのにも意味はあったけれど、
ラベルがあることで自分はマイノリティなんだと思うことは、とても孤独でした。
ラベルを超えて、もっと広い視点で語れる言葉を探していたときに出会ったのがSOGIでした。
誰もがそれぞれに違って、それぞれにSOGIを持っている。
そう思ったら、ただみんなが同じSOGIの中にいて、それぞれに個性があるだけなのだと思えました。
SOGIを知ることで、違いを自然に受け止められる社会へ
ラベルより先に、「感覚」から理解することの大切さ
「LGBTQってよく聞くけど、たくさんあってよくわからない」
そんな声を聞くことがあります。
確かに、ラベルや分類は多様で、言葉としての整理は難しく感じるかもしれません。
でも、だからこそ、“わからないけど、みんなちがう”という前提を持つことが大切だと思うのです。
ラベルはあくまで「後からつける名前」であって、
最初にあるのは、その人の「感覚」や「生きづらさ」や「心地よさ」のはず。
SOGIという視点は、
「この人はバイセクシュアルだからこういう人」ではなく、
「この人なりの性の感覚があるんだ、きっと私とは違うんだな」と、
“わからないこと”をそのまま受け止めるやさしさを教えてくれます。
教育・職場・家庭でどう広める?伝え方のヒント
SOGIはとてもパーソナルな感覚ですが、
だからこそ「特別な場面」でだけ語るのではなく、
日常の中で、少しずつ「自分ごと」として話せる空気づくりが大切です。
たとえば、
- 学校で「自分のSOGIを考えてみよう」という時間を作る
- 家庭で「どんな恋愛もどんな性自認も間違いじゃない」と話す
- 職場で「自分らしく働ける環境ってどんなだろう?」と考える
知識として教えるだけでなく、
「あなたにもあるよね」という共通点から話すことで、
“当事者”という言葉の枠を超えた対話が生まれます。
“あの人”ではなく、“わたし”の話としてSOGIを語ろう
わたしが「SOGIって大切だな」と感じたのは、
ラベルを持っていない人にも届く言葉だからです。
「ノンバイナリー」「アセクシュアル」と名乗らなくても、
「なんとなく、みんなとちがうな」「性や恋愛にモヤモヤがあるな」
そんな思いをしている人は、きっとたくさんいるはず。
そういう人に、「あなたの話でもあるんだよ」と伝えられるのがSOGIという言葉。
誰かを理解するためだけじゃなく、自分自身を知るきっかけにもなる。
それが、SOGIの本当の力なんじゃないかと思っています。
もっと学びたい人へ|SOGI・セクシュアリティの関連記事
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
SOGIという言葉を通して、「性のあり方は誰にでもあるもの」という視点に少しでも触れていただけたなら、とても嬉しいです。
とはいえ、「性的指向」や「性自認」といった言葉にはまだまだ広がりがあり、
人によって感覚や言葉の捉え方もさまざまです。
ここでは、SOGIと関連の深いセクシュアリティの概念や体験談を紹介している記事をいくつかご紹介します。
「自分の感覚って何なんだろう?」と思ったときのヒントとして、ぜひあわせてご覧ください。
関連記事



性に関する話題は、ときに難しさや恥ずかしさを感じることもあります。
でも、「自分がどう感じているか」に目を向けることは、決して間違ったことではありません。
自分の感覚を否定せず、誰かの感覚も尊重し合える社会に向けて。
SOGIという言葉が、その一歩になることを願っています。
あなたは、あなたのままでいい。