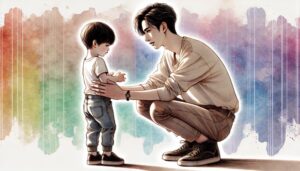「男の子だから泣かないの」「女の子なんだからおしとやかに」 そんな言葉に、ちょっと違和感を覚えたことはありませんか?
最近、海外を中心に注目されているのが「ジェンダー・ニュートラル育児(gender-neutral parenting)」という考え方。
これは、子どもに最初から「男の子」「女の子」というラベルを貼るのではなく、子ども自身が“自分らしさ”を見つけられるように育てていこうというスタイルです。
今回は、最新の研究や海外の事例を交えながら、「ジェンダー・ニュートラル育児」の考え方や実践方法、そして実は我が家でも自然に取り入れていたことを紹介します。
ジェンダー・ニュートラル育児とは?その意味と背景
「ジェンダー・ニュートラル育児」とは、性別にとらわれない自由な育て方のこと。
- 子どもに「男の子だから〇〇」「女の子なのに〇〇」と言わない
- 好きな服やおもちゃを性別で制限せず、子どもが好きなものを選ばせる
- 一人称(わたし/ぼく など)をあえて矯正しない
など、親の価値観を押しつけるのではなく、子ども自身が選んでいける余白を残す育児スタイルです。
海外では、子どもに性別を伝えずに育てる家庭もあり、「theyby(ゼイビー)」と呼ばれることもあります。
これは、“they(彼ら・彼女ら)”という中立的な代名詞を使って育てるという意味から来ています。
どんな人たちがこの育て方をしているの?
この育児法を実践しているのは、以下のような方たちなんだそう。
- 自身がノンバイナリー・トランスジェンダーである人
- ジェンダーにまつわる固定観念に疑問を持っている人
- 子どもの選択肢を広げたいと考えている人
- 教育や発達心理に関心のある人
「男の子なのにピンクが好き」「女の子なのに虫が好き」といった子どもを見て、 「自分らしくあっていい」と受け入れたいと考える親たちが増えてきています。
研究でわかってきたこと:性別にとらわれない育児の効果と課題
Rahilly(2022)の実態調査
米国の社会学者エリザベス・ラヒリー博士(Elizabeth Rahilly)は、21組の親と11組の祖父母を対象にした質的インタビュー調査を実施し、ジェンダーにとらわれない育児スタイルの実態を報告しました。
この研究によると、多くの家庭で以下のような方針が見られました:
- 子どもに性別ラベルを与えない
- 出生時の性別を意図的に秘密にする
- 子どもに対してthey/them という代名詞を使用する
ラヒリー博士はこの育児スタイルを「Gender-Open Parenting(ジェンダー・オープン育児)」と定義し、親たちが性別固定観念に抵抗しながら、より開かれた育児方針を選択していることを指摘しています。
出典:Rahilly, E. (2022). Gender-Open Parenting: Raising and Resisting Gender in Contemporary Families, Journal of Family Theory & Review, 14(3).
非バイナリー・トランス親の調査(2022年)
別の学術研究では、非バイナリーやトランスジェンダーの親たちを対象にした実態調査が行われ、約56%の回答者が「子どもに性別ラベルをつけずに育てている」と回答しました。
この調査では、次のような育児方針が見られました:
- 子どもの遊びや活動を性別に制限しない
- 好きな服やおもちゃを自由に選ばせる
- 自己表現の幅や柔軟性、自己肯定感が育まれているという観察的報告
ただし、この研究は主にインタビューとアンケート形式によるものであり、統計的な因果関係を示すものではありません。
出典:Non-binary and Trans Parenting Report (2022)
心理学研究:性役割に縛られない遊びの効果
心理学の視点からも、性別固定にとらわれない環境が子どもの発達に好影響を与える可能性が示唆されています。
米国の心理学専門誌『Psychology Today』の記事では、玩具や服を性別で制限せずに自由に選ばせると、子どもはより多様な自己表現や創造性を見せる傾向があるとされています。
これは「Gender-Creative Parenting(ジェンダー・クリエイティブ育児)」と呼ばれるアプローチで、「子どもが自分のペースで性を探索できる環境」を意識的に整えるものです。
出典:Gender-Creative Parenting Lets Kids Be Kids, Psychology Today
英国LOGIC研究
イギリスでは、性別の自己認識とメンタルヘルスの発達に関する長期的研究として「LOGIC研究(Longitudinal Outcomes of Gender Identity in Children)」が進行中です。
この研究は、性別に違和感を持つ若者(Gender Diverse Youth)とその家族を対象に、心理的健康、自己肯定感、社会的サポートの影響などを複数年にわたって追跡調査するものです。
特に注目されているのは、次のような点です:
- 性別の選択・表現の自由とストレスレベル・自己肯定感の関連
- 社会的サポート(家族・学校・医療体制)の有無がメンタルヘルスに与える影響
このような長期研究は、ジェンダー・ニュートラル育児やトランス・ノンバイナリーの若者支援における実証的なエビデンスとして注目されています。
出典:Steensma, T. D., Biemar, C., et al. (2021). Understanding gender identity development in children and adolescents: insights from the LOGIC study. Archives of Sexual Behavior, 50(5), 1861–1875.
実は我が家も自然に取り入れていた?
私自身、「ジェンダー・ニュートラル育児」という言葉を知ったのは最近です。
でも振り返ってみると、日常の中で自然と取り入れていたことがありました。
たとえば:
- 上の子が「おねえちゃん」と呼ばれることに違和感があり、家族に“名前で呼ぶ”ようにお願いしていた
- 服のデザインは男の子向け・女の子向けに関係なく、「子どもの好きなものを選ぶ」ことを大切にしていた
- 子どもが「私」「ぼく」とさまざまな一人称を使っても、直さず見守っていた
- 虫や花が大好きなので、周りからは「女の子なのに虫が平気なのね」といった声があっても、好きなようにさせている。
こうしたことは、“子どもが自分で選べるようにしたい”という自然な気持ちから出たもので、知らないうちに実践していたのだと思います。
今日からできる、ジェンダー・ニュートラル育児のヒント
- おもちゃや服を選ぶとき、「どれが好き?」と本人に聞く
- 性別に結びつく呼び方(おにいちゃん/おねえちゃん)を見直す
- 多様な性や家族が描かれた絵本を一緒に読む
- 「男の子なんだから」「女の子らしく」などの言葉を無意識に言っていないか確認する
ジェンダー・ニュートラル育児のヒントが子どもたちにどんな未来をもたらすのか、
これからも見守っていきたい
「ジェンダー・ニュートラル育児」が正しい・間違っているという話ではなく、 こうした考え方や実践があることを知っておくことに意味があると思います。
自分らしくいられる子どもたちが、どんなふうに育っていくのか。
このテーマに、私はこれからも静かに関心を寄せながら、見守っていきたいと思います。